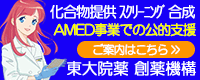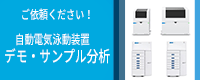ご挨拶
 第46回日本分子生物学会年会
第46回日本分子生物学会年会年会長 林 茂生
(理化学研究所・生命機能科学研究センター)
2023年会長最後のご挨拶
「巨大な雑談室へようこそ」をキャッチフレーズにした第46回日本分子生物学会年会はオンラインとオンサイトの11月27日-12月8日の開催を無事に終えることができました。参加者数は6,700名におよび、シンポジウム、ポスター、フォーラムなどで約4,500件の演題が発表されました。ご参加いただき盛り上げてくださった皆様に深く感謝申し上げます。
また本年会は194社の協賛企業からサポートなくしては実現できませんでした。温かいご支援に御礼申し上げます。
振り返れば当時の杉本亜砂子理事長から打診を受けた2019年に構想を始め、2020年の年会長であった上村匡さんと年会スタッフに同行させていただき、候補地であった神戸の会場を視察しました。運悪くCovid19の蔓延により2020年の年会はオンライン開催となりましたが今回の開催では一部会場にスクリーンを二組設置した横長使用や、通勤ラッシュを避けてシンポジウムを9時半開始にするなど、上村さんのアイデアを生かさせていただきました。企画当初はまだ猛威を振るっていたCovid19にどう対応するかが課題でした。幕張年会の結果からもオンサイト参加が熱望されていることがわかっていましたが、生命科学の学会で感染が広がってしまったらシャレにもならないのでオンライン、オンサイトの二本立てで保険をかけることにしました。ハイブリッドの選択肢も検討しましたが講演会場では発表者と聴衆が直接対峙することが良い緊張を生むとの私の考えと、コストの問題を考慮して今回は見送りました。3箇所に分散する18のシンポジウム会場を移動してお望みの講演を聴くことは大変だったと思いますが、一期一会の出会いを得ることも学会の楽しみだと思います。大小様々なサイズの会場がいずれも熱気あふれる聴衆と講演で賑わいました。会場によっては満員で廊下に追加したモニターも足りなくなってしまいご迷惑をおかけしました。会場が狭く座れない、とのお叱りを多数頂戴しましたが伏してお詫び申し上げます。
年会本部は10本のオンライン企画シンポジウムを立て、ウォーミングアップしていただくこととしました。オーガナイザーにはこれまで近いようで交流がなかったような方々を組み合わせて化学反応が起きるような仕掛けをいたしました。細胞初期化を扱う動物、植物の研究者をお招きした[O-1PS-01]動植物初期化原理、表現型多形とエピジェネティクスの専門家が対した[O-4PS-01]表現型可塑性、などがその例です。いかがでしたでしょうか?ポスター発表にも多数の演題登録をいただき、できる限りアピールの機会を増やしたいとの意図で昨年に続きショートトーク(サイエンスピッチ)を開催し、11会場で合計534演題のトークを行なっていただきました。会場毎での審査で表彰を行うとともに、特に評価が高かった演題5件にEMBO Pressと分子生物学会年会から特別賞を贈りました。希望者のポスター発表をEMBO PressのChief EditorのBernd Pulverer博士らが審査するEMBO Poster Clinicでは遅い時間まで熱い討論が繰り広げられ、EMBO Pressと分子生物学会から1件ずつの表彰が行われました。結果については年会ホームページをご覧ください。年会企画の一つとして行われた「サイエンスイラストレーターのお仕事展」では15個人、団体に展示と営業を行なっていただき、会期を通して賑わいました。MBSJ-EMBO合同企画ランチョンセミナー「あなたの論文はどこへ行く:論文出版とオープンサイエンスに関する対話」で議論した内容はGenes to Cellsに報告しています。オープンアクセスですのでどなたにもご覧いただけます(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gtc.13100)。
一方で残念なことに、年会においてハラスメントと受け取られる事例が複数報告されました。学会参加者の多くは所属機関の公務出張で参加しており、ハラスメント禁止などの本務先での服務規程が及びます。学会は研究交流の場であるとともに個人や、研究室が相互評価を行う場でもあり、品位を欠く振る舞いは、本人のみならず所属機関と研究室の評判を下げることにもつながりかねません。自由闊達なサイエンスの議論を妨げることのないように参加者の皆様、特に指導者の方々にはいま一度ご注意をお願いいたします。
今回の分子生物学会でも高校生の発表をオンラインとオンサイトで行いました。深い考察がなされる研究も多く、発表のポスター会場は大会で最も密で熱い空間でした。英語で行われたランチョンセミナーでは真っ先に立ち上がってコメントする生徒もいて、サイエンス新人類の誕生を予感しました。私自身会場を歩き回って各所で討論しましたが、学ぶことが多く有意義な議論ができました。最近になって日本の科学研究の退潮を示す数字が報道され悲観的な見方が出ています。現状に安住せず危機感で戒めることは大切ですが、一方で若い人が集う学会では科学の可能性の広がりと明るい未来への展望を見せることが何よりも大事です。そのような役割を今回の年会で果たせたとしたらうれしいことです。
2024年2月
10月になりようやく暑かった夏が終わった感があります。それにしても夏が長すぎはしませんかね〜?さて年会に向けて「巨大な雑談室へようこそ!」というキャッチフレーズを用意しました。学会はフォーマルな発表の場だけではなく、旧知の友人、論文で名前を知った憧れの研究者、全く別分野の研究者などとランダムに出会い、雑談を通じてサイエンスのアイデアと気づきを得る貴重な場でもあります。今年も大判の名札を採用し、そこに貼り付けられる研究分野を象徴するイラストのシールを用意します。自分だけの名札をデコって出会いのチャンスを増やしてください。
Late Breaking Abstract(LBA)の応募が締め切られ、大会の発表数が固まりました。一般演題:2,270演題、LBA:623演題、合計:2,893演題となり2018年の横浜大会とほぼ同等の数でパンデミック前のレベルに戻った感があります。特にLBAの数は過去最大数となり、最新の研究成果が数多く報告されることを楽しみにしています。ポスターセッションでは一般演題とLBAの区別なしで配置する予定です。また参加者のアピールの機会を増やしていただくために一般演題の中からシンポジウムに237件を採択して頂き、フラッシュトークのサイエンスピッチはポスター会場の特設ステージで544演題もの発表が行われます。シンポジウムはオンライン18件、オンサイト107件が予定されており、19件のフォーラムも開催されます。必ずやあなたの仕事に役立ち、好奇心を満たすセッションがあるはずです。
今年もEMBOのご協力でポスタークリニックが行われるので奮ってご参加ください。そして激動化の時代を迎えた科学論文出版を見据えてEMBO publishingとGenes to Cellsの編集者を招いてのScientific Publicationの将来に関するランチョンセッションが12/8に予定されています。さらにフォーラム枠を用いて科学コミュニケーションのセッションを二日続けて行います。これに連動してサイエンスイラストレーターの方々のお仕事をポスター展示して頂き、研究者との交流とお仕事依頼などの場として活用する企画を用意します。科学コミュニケーターとコミュニケーションを深めることで研究成果の発信にお役立てください。
年会は11/27(月)からのオンラインシンポジウムで始まります。9:00からと16:00からの朝夕配信で1ヶ月を目処にオンデマンド配信も行います。朝からガッツリ視聴もよし、お仕事の合間、出張の車内で気楽にザッピングされるもよし、スキマ時間にオンデマンド視聴もよしなので、ぜひお楽しみください。
Covid19が5類に移行し街ではマスク姿の人々の数も減りつつあります。しかし最近になってコロナやインフルエンザ感染のニュースが頻発し、私の周辺でも感染の報告は後を断ちません。私も用心のためにCovid19とインフルエンザの予防接種を受けました。会場ではマスクの無料配布、演台へのシールド設置などの対策を講じます。せっかくのオンサイト学会で感染してしまうことのないように会員の皆様方も十分な備えの上でご参加いただくことをお願い申し上げます。
2023年10月
皆様、公募シンポジウムに対しては多数のご応募を頂きありがとうございました。その大半は現地での開催を希望されており、オンサイト大会に対する会員の要望と熱意を強く感じました。会員のアイデアと提案を生かすことが年会の最優先事項であると考えて、急遽会場を追加して、一部のご提案はフォーラムで行っていただくことで全提案をうけいれることに致しました。調整の要請に応じてくださったオーガナイザーの皆様には感謝申し上げます。
また参加登録費の設定を行いました。昨年の参加登録費の値上げを受けてアンケートへのご回答には、許容できるという意見もあればもう参加したくないとの厳しい意見まで、実にさまざまなご意見を頂きました。もう一点アンケートの分析で特徴的だったのは年会に研究費ではなく自費で参加しておられる方が4分の1程度いらっしゃることでした。研究費の厳しい事情もあれば、職務とは別に自己研鑽のために参加される方も多いのだろうと思われます。これらの点を考慮して正会員の事前参加登録費(7/3~10/10)を昨年よりも引き下げて¥13,000 と致します。後期登録、当日参加は昨年通りの¥20,000 と致しますので事前登録をお忘れないようにお願い致します。
シンポジウムの応募要項では女性比率を30% 程度として、予定演者の性別を記載するようにお願いしました。これに対して複数の会員から「自身の性別の明示を強いられることを苦痛に感じる人がいる」との指摘を受けました。確かに最近の各種登録メニューには female/male/prefer not to say といった三種以上の選択肢が用意されていることが多いです。苦痛に感じられた方にはお詫び申し上げます。性別の確認は女性の参加比率を向上させるとの分子生物学会の方針を受けてのことでした。組織委員会での議論では男性―女性間のジェンダーギャップの解消が喫緊の課題であることは確かだが、このカテゴリーに収まらないマイノリティーの存在も忘れてはいけない。特定のグループ(性別、人種、出身大学など)がover-represent しないような配慮が本質である、との理解に収束しました。今後の対応に活かしていきたいと思います。
一般演題(公募シンポジウム口頭発表・サイエンスピッチ(ショートトーク)・ポスター)の登録が7/3 から開始します。
締め切りは7/31(月)17:00 で、延長はありません。また海外若手研究者招聘企画として海外在住会員への渡航費援助も行います(締め切り7/31)。お忘れなきよう、奮ってご登録をお願い致します。
2023年6月
皆さん、昨年末の第45回年会はいかがでしたでしょうか? 私自身は幕張メッセの広大な会場を活用したさまざまな企画を見て、参加して大いに楽しませてもらいました。深川年会長をはじめとする運営委員の皆様のアイデアと多大なご尽力に深く感謝致します。会員の方からの意見も集めていますが大いに評価される声が多く、成功したアイデアは改善を加えて次回にも生かしたいと考えています。さて学会の年会機能の中核は研究成果を発表し、自由闊達に相互批判を行う事です。また生命科学系最大規模の分子生物学会では、自らの研究分野から踏み出して日常では触れることのない分野の話題を学ぶことで研究の展開を図り、未来の共同研究者を発見する機会となるはずです。年会本部として企画をお願いした指定シンポジウムではオーソドックスな分子生物学から踏み出した研究の話題が含まれています。またコアな話題においては新たな化学反応を期待してちょっとかけ離れた領域からオーガナイザーをお招きしたものもあります。会員が工夫を重ねて提案していただく公募シンポジウムとフォーラムとを合わせて楽しめる年会を企画していきます。
幕張年会においての次期年会長としてのお仕事として、企業ブースを回っての挨拶があります。出展者とお話しをして年会の感想と希望を伺ってから翌年の出展をお願いします。二日間をかけてほぼ全てのブースを回ることはなかなかの荒行でしたが、各企業の推しの製品説明を伺うことで技術開発の動向を把握する事ができ、過去に取引があった会社の担当者からご挨拶を頂いて顧客を大事にされている姿勢を感じました。また過去に研究者として活躍されていた方が企業のスタッフとして年会に参加されているケースも数多く見る事ができました。年会予算の大きな部分は企業協賛金でまかなわれています。私たちの研究は企業が提供する試薬と機器を用いて遂行され、研究室の卒業生の多くは関連企業に職を求めます。年会の場において研究者と協賛企業がより深く知り合うことで分子生物学の研究は更に活性化し、分野は広がり、深まるはずだと考えて、両者の交流が深まる工夫を用意したいと考えています。
会員の皆様には昨年の年会で得た刺激とアイデアを生かした研究を進め、今年の神戸年会で発表していただくことを楽しみにしています。
2023年1月
2023年の第46回年会長を務めさせていただきます、理化学研究所の林茂生です。この3年間は全世界の人々がCovid19のパンデミックに振り回されてきました。まだ感染が収束したとは言えませんがワクチンの接種や、感染対策が日常生活に定着したことで今年になってからようやくオンサイトの学会も各地で開かれるようになりました。私も5−6月に海外の学会に出席し直接議論を交わして交流を深め、専門家の率直な感想を得る事のありがたさを実感しました。9月に行われた国内学会ではポスター会場で呼び止めた初対面の研究者との議論が弾んで共同研究に発展すると言うおまけまでついてきました。直接話し合う事による情報の密度、議論の深みと予期せぬ出会いがやってくる事にこそオンサイト学会を開く価値があります。一方でパンデミックを体験した社会は元には戻りません。オンラインミーティングや在宅勤務の普及は家庭の事情などで出張がかなわない人たちが研究を続けることを可能にしており、Covid19が収束した後でも新しい研究スタイルとして定着することでしょう。会場に来ていただける方だけではなく、会場に来れない方に対しても年会に参加する実感を体験してほしいと考えます。そこで組織委員会の議論を踏まえて第46回年会はオンサイト+オンライン併用のフォーマットを採用します。まず11月27日から5日間をオンライン週間としてシンポジウムを開催します。午前、午後に時間帯を分けることで海外の演者にも参加しやすく出来ると思います。またオンデマンド視聴を用意する事で聞き逃しなしに、興味ある演題を何度でも聞いてください。その上で12月6日−8日のオンサイト開催に来ていただくようにお願いいたします。ハイブリッドではなくオンサイト+オンライン併用としたのは1度限りのオンサイトの緊張感を大事にしたいということと、会場運営をシンプルにする事で通信障害などによるトラブルを減らしたいとの意図があります。会場は神戸ポートアイランドです。皆さん、セレンディピティを求めて神戸の街にお越しください。
2022年11月