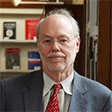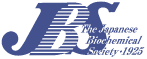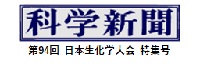日程表
・日程表
特別講演
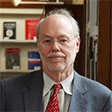
Phillip A. Sharp(Massachusetts Institute of Technology)
日時:11月3日(祝・水) 13:50~14:40
司会:深水 昭吉(筑波大学)

水島 昇(東京大学)
日時:11月4日(木) 13:50~14:40
司会:谷本 啓司(筑波大学)
シンポジウム
シンポジウム一覧
<セッションNo.について>
開催日+シンポジウム(S)+会場+時間帯*
(例)1S02m:第1日目・シンポジウム・第2会場・9:00-11:00
*時間帯表示の凡例
シンポジウムが行われる時間枠によって表示が区別されます
m: 9:00-11:00
a: 14:50-16:50
e: 17:00-19:00
1S01m
日 時:11月3日(水)9:00-11:00 会 場:第1会場 (G303+304)
人生100年時代の「老い」を考える
オーガナイザー:佐田 亜衣子 (熊本大学)、森 英一朗 (奈良県立医科大学)
講演者・概要▼
講演者:佐田 亜衣子 (熊本大学)、佐藤 亜希子 (国立長寿医療研究センター)、早野 元詞 (慶應義塾大学)、荻沼 政之 (大阪大学)、廣田 恵子 (東京女子医科大学)、松崎 京子 (東京医科歯科大学)、柴田 淳史 (群馬大学)、森 英一朗 (奈良県立医科大学)、本庶 佑(京都大学)
概 要:いつまでも若々しく、健やかに生きることは、人類の長年の願いである。酵母、線虫、ショウジョウバエ、哺乳類を用いた個体レベルの解析により、適切な運動や食事、睡眠、生殖が、老化を制御する鍵として提唱されている。分子レベルでは、加齢に伴い、DNA損傷、エピゲノム変化、代謝やプロテオスタシスの異常等が、単独または複合的に起こり、組織の機能低下や病変の一因となることが明らかにされつつある。1つの細胞内で起こる変化は、細胞外へと伝達され、臓器・個体レベルで時空間的に情報が統制される。しかし、老化に関する知見の多くは、特定の臓器や分子に着目した個別研究であり、老化プロセスを統合的に理解し、議論するための基盤が不足している。本シンポジウムでは、細胞内外の多様な生体分子を扱う研究者が一堂に集い、「老化」現象の階層的、横断的な理解を深め、人生100年時代を健やかに生きるストラテジーについて考察する。
1S02m
日 時:11月3日(水)9:00-11:00 会 場:第2会場 (G404)
代謝動態学~代謝物の時空間情報を取得するバイオイメージングの技術と実践~
オーガナイザー:西川 恵三 (同志社大学)、山本 正道 (国立循環器病研究センター )
講演者・概要▼
講演者:今村 博臣 (京都大学)、山本 正道 (国立循環器病研究センター)、西川 恵三 (同志社大学)、杉浦 悠毅 (慶應義塾大学)、加納 英明 (九州大学)
概 要:代謝ネットワークは、エネルギーやバイオマスを産生する生命活動に欠かせないインフラであるだけではなく、細胞の運命決定を複雑かつ巧妙に調節するための重要な分子基盤である。細胞は、外界と物質を授受する開放系であり、その中では絶え間ない酵素反応の連鎖によって膨大な代謝物の生成と消費が引き起こされる。これらの代謝物がいかにして生命を作り上げているかを正確に捉えるには、代謝物の動態を直接的に見ることの意義は大きい。本シンポジウムでは、細胞あるいは生体に対して代謝物の動態をありのままに観察するイメージング法の最新の動向として,代謝物を可視化するためのバイオセンサーの開発や様々なバイオイメージングの実践応用について取り上げる。
1S03m
日 時:11月3日(水)9:00-11:00 会 場:第3会場 (G403)
マルチファセット・プロテインズ:拡大し変容するタンパク質の世界
オーガナイザー:田口 英樹 (東京工業大学)、永井 義隆 (大阪大学)
共催:学術変革領域研究(A) マルチファセット・プロテインズ:拡大し変容するタンパク質の世界
講演者・概要▼
講演者:松本 雅記 (新潟大学)、松本 有樹修(九州大学)、遠藤 斗志也(京都産業大学)、田口 英樹 (東京工業大学)、永井 義隆 (大阪大学)
概 要:この数年間での発見や技術革新により、従来のタンパク質像が揺らいでいる。例えば、非典型的な翻訳が普遍的に起こるため、タンパク質の種類は急激に増加している。また、細胞内でのタンパク質の機能発現様式も多様であることがわかってきた。つまり、タンパク質の世界において従来見えていなかった多くの面(マルチファセット)が見えはじめている。この拡大し変容しつつある真のタンパク質像を理解するためには、マルチファセットにタンパク質の世界を捉えなおす必要がある。そこで本シンポジウムでは、新しいタンパク質の世界を開拓している研究者に最新の知見を講演してもらった上で、拡大し変容しつつあるタンパク質の世界の今後について議論する。
1S04m
日 時:11月3日(水)9:00-11:00 会 場:第4会場 (G402)
疾患における生命金属動態の破綻と創薬
オーガナイザー:石原 慶一 (京都薬科大学)、豊國 伸哉 (名古屋大学)
共催:新学術領域「「生命金属科学」分野の創成による生体内金属動態の統合的研究」
講演者・概要▼
講演者:豊國 伸哉 (名古屋大学)、藤田 宏明 (京都大学)、菅波 孝祥 (名古屋大学)、保住 功 (岐阜薬科大学)、石原 慶一 (京都薬科大学)
概 要:鉄、亜鉛、銅、ホウ素など生命体に微量に存在する金属元素や半金属元素(生命金属と定義)は、エネルギー産生、物質輸送、情報変換など重要な生命現象に関わっており、あらゆる生物の生命を維持する上で必須である。すなわち、生命金属の体内動態の破綻は、生命活動の維持に影響を及ぼし疾患の原因となる。本シンポジウムでは、生命金属の体内動態の破綻が関与する疾患として“がん"、“神経変性疾患"、“ダウン症候群"および“肝線維化"を紹介し、創薬標的としての可能性について議論したい。
1S05m
日 時:11月3日(水)9:00-11:00 会 場:第5会場 (G401)
「核とミトコンドリア研究」から視えてきた疾患病態の先端生化学
オーガナイザー:田中 知明 (千葉大学)、井上 聡 (東京都健康長寿医療センター研究所)
講演者・概要▼
講演者:田中 知明 (千葉大学)、池田 和博 (埼玉医科大学)、伊藤 敬 (長崎大学)、栗本 遼太 (東京医科歯科大学)、重本 和宏 (東京都健康長寿医療センター研究所)、松井 秀彰 (新潟大学)
概 要:ミトコンドリアは独自のゲノムを持ち、核ゲノムにコードされた特定の遺伝子をうまく利用しながら、細胞内小器官としての多彩な機能を発揮する。従って、転写や翻訳、エピゲノム制御機構の中心となる核内事象と相まって、それらの生化学的先端研究は、生老病死の病態を紐解く鍵となる。一方、寿命(lifespan)という観点からは、テロメア、DNA損傷、酸化ストレス、サーチュイン、栄養、代謝などの老化シグナルは共通して核とミトコンドリアに集約する。本シンポジウムでは、「核とミトコンドリアの生化学研究」をテーマに、シングルセルや複合体解析・トランスオミクス解析など新たなアプローチを通じて、転写制御や代謝調節の視点から疾患病態との関わりを切り開いてきた先駆的研究を紹介する。核とミトコンドリアのシナジーから紐解く疾患病態生化学について、これから切り開かれゆく新たな可能性も含めて皆さんと議論を深めたい。
1S06m
日 時:11月3日(水)9:00-11:00 会 場:第6会場 (G302)
哺乳類の代謝変動による環境適応とその異常
オーガナイザー:木村 航 (理化学研究所)、有馬 勇一郎 (熊本大学)
講演者・概要▼
講演者:有馬 勇一郎 (熊本大学)、山口 良文 (北海道大学)、田中 都 (名古屋大学)、木村 航 (理化学研究所)、林 悠 (京都大学)
概 要:哺乳類はその恒温性などに代表されるように,外部環境の変化にかかわらず内部環境を一定に保つ能力に長けている.このように一見したところ同じに見える内部環境を保つ能力は,実際には外部環境の変化を感受し,それに応答して代謝状態をはじめとした内部環境を変化させる能力と表裏一体である.哺乳類がライフサイクルの中で経験する日周期や季節性,または出生や成長・病的環境などの大きな環境の変動への応答のメカニズムの解明は,疾患に立ち向かう予防医学や新規治療法開発に向けた示唆に満ちている.本シンポジウムではさまざまな動物種,ライフステージのモデル生物を使い,環境の変動に対する適応のメカニズムについて個体から細胞までの階層をつなぐ研究を展開している若手研究者による講演を行う.
1S07m
日 時:11月3日(水)9:00-11:00 会 場:第7会場 (G301)
核小体の構造と機能の新たな発見
オーガナイザー:奥脇 暢 (北里大学)、木村 圭志 (筑波大学)
講演者・概要▼
講演者:奥脇 暢 (北里大学)、木村 圭志 (筑波大学)、常岡 誠 (高崎健康福祉大学)、小藤 智史 (東京医科歯科大)、井手 聖 (遺伝学研究所)
概 要:核小体は光学顕微鏡でも容易に観察できる膜を持たない核内構造体(核内ボディ)である。古くから、核小体はリボソーム生合成の場として知られてきたが、近年、細胞分裂期制御、細胞老化、RNP複合体形成制御、ストレス応答など、多様な機能を持つことが明らかになってきた。また、核小体の構造や機能の異常が、がんや神経変性疾患など、ヒトの疾患とも深くかかわることも明らかになりつつある。したがって、核小体形成の分子機構やその多様な機能の詳細を解明することは、生物学的な観点のみならず、医学・薬学的な観点からも非常に重要である。また、核小体は、単なる凝集体ではなくその構成因子は非常に流動的な性質を持ち、細胞ストレスや細胞周期の過程でダイナミックな構造変化をする。最近になって、核小体形成に液-液相分離が関わることが注目を集めている。 本シンポジウムでは、液-液相分離による核小体の構造形成機構の詳細、核小体の新たな機能、核小体と疾患とのかかわりについて、最新の研究成果をもとに議論を深めていきたい。
1S08m
日 時:11月3日(水)9:00-11:00 会 場:第8会場 (G312)
先端技術を用いた食事・栄養成分を介した免疫-代謝ネットワークの理解と応用
オーガナイザー:國澤 純 (医薬基盤・健康・栄養研究所)、長谷 耕二 (慶應義塾大学)
講演者・概要▼
講演者:國澤 純 (医薬基盤・健康・栄養研究所)、長谷 耕二 (慶應義塾大学)、高橋 伸一郎 (東京大学)、中川 嘉 (富山大学)
概 要:世界中に新型コロナウイルスが広がり、社会情勢が大きく混乱している中、改めて生体防御システムとしての免疫の重要性が認識され、また糖尿病などの代謝性疾患とウイルス感染時における病態との関連も注目されている。これら免疫や代謝の制御における食事・栄養成分の重要性は古くから知られていたが、その多くは曖昧模糊としたものであった。しかしながら、近年の分析技術の発展もあり、その詳細な制御メカニズムが議論できる時代になってきた。本シンポジウムでは、生化学的手法を含めた複数の解析技術により、「免疫・代謝・栄養」の相互関連を明らかにする先駆的研究を進められている演者に講演いただき、新しい融合領域としての将来展望と生化学の可能性について議論したい。
1S09m
日 時:11月3日(水)9:00-11:00 会 場:第9会場 (G313)
認知症発症のリスクとメカニズムの多様性:アルツハイマー病の高精度診断法と治療法開発に向けて
オーガナイザー:飯島 浩一 (国立長寿医療研究センター )、道川 誠 (名古屋市立大学)
講演者・概要▼
講演者:重水 大智 (国立長寿医療研究センター)、菊地 正隆 (大阪大学)、関谷 倫子 (国立長寿医療研究センター)、山崎 雄 (広島大学)、道川 誠 (名古屋市立大学)
概 要:認知症の最大の原因であるアルツハイマー病(AD)は,脳内に蓄積したアミロイドβ(Aβ)ペプチドが,慢性的な神経炎症,脳血管系の破綻,タウ病変の拡大,そして不可逆的な神経細胞死を引き起こし発症に至る。近年,Aβやタウを標的とした脳画像診断法に加え,血液診断法の開発が世界中で進み,ADを発症前に捉える超早期診断が実現されつつある。ADを高精度に診断・分類し,的確な予防・治療法を開発するためには,人種特異性や遺伝的背景の違いを考慮し,AD発症メカニズムの多様性を解明することが重要となる。本シンポジウムではAD研究の最前線で活躍する研究者をお招きし,日本人ゲノム解析から新たな危険遺伝子の発見,AIを用いたAD発症予測,さらに遺伝子ネットワーク解析を用いた治療薬探索についてお話しいただく。さらに,AD最大のリスク因子であり,治療標的としても再注目されているAPOEの最新の研究についても議論する。
1S10m
日 時:11月3日(水)9:00-11:00 会 場:第10会場 (G314)
免疫における転写および転写後調節ネットワーク
オーガナイザー:酒井 真志人 (日本医科大学)、吉田 英行 (理化学研究所)
講演者・概要▼
講演者:幸谷 愛 (東海大学)、伊川 友活 (東京理科大学)、二村 圭祐 (大阪大学)、吉田 英行 (理化学研究所)、酒井 真志人 (日本医科大学)
概 要:免疫システムは精密に制御された防御メカニズムとして感染症防御や腫瘍細胞の排除に働き、その破綻は日和見感染症や自己免疫疾患、自己炎症性疾患、腫瘍の増殖など、様々な疾患につながる。免疫システムでは多種多様な免疫細胞が様々な機能を担っており、免疫システムの理解を進めるため免疫細胞の機能が多面的に研究されてきた。最近のゲノミクスとシングルセル解析の技術的な進歩は、免疫細胞の機能を調節する転写および転写後制御ネットワークの理解を、これまでにない速度で進ませており、DNAメチル化やクロマチン修飾、高次クロマチン構造、転写因子、非コードRNA、転写後調節因子等が協調的に働き遺伝子発現が制御されることが明らかになってきている。本シンポジウムでは、独自のアプローチで免疫細胞の転写とRNA制御の解明に取り組む研究者の最新の知見を紹介し、多角的な視点から議論したい。
1S11m
日 時:11月3日(水)9:00-11:00 会 場:第11会場 (G315)
レドックス生物学におけるアダクトエクスポソームの重要性
オーガナイザー:熊谷 嘉人 (筑波大学)、上原 孝 (岡山大学)
講演者・概要▼
講演者:上原 孝 (岡山大学)、伊藤 昭博 (東京薬科大学)、鈴木 孝禎 (大阪大学)、堂前 直 (理化学研究所)、どど 孝介 (理化学研究所)
概 要:親電子物質は反応性システイン残基を有するセンサータンパク質に共有結合して、レドックスシグナル伝達を活性化(低用量)および破綻(高用量)する。一方、細胞内において、安息香酸のような保存料が細胞内基質として誤認され、ヒストンのリジン残基を介して化学修飾することでエピゲノム変化を生じることが話題になっている。一連の研究成績は、生活環境、ライフスタイルや食生活を通じて、生体内に取り込まれた化学物質により細胞内の脱プロトン化しやすい求核置換基が化学修飾され、それが起点となってエピゲノム変化やレドックスシグナル変動を生じる可能性を示唆している。本シンポジウムでは、ヒトの生涯における環境曝露の総体である「エクスポソーム」を研究する一環として、タンパク質の化学修飾能を有する被験物質を対象とした“アダクトエクスポソーム"のモデル化を推進する研究者達の戦略と最新の成果を概説する。
1S12m
日 時:11月3日(水)9:00-11:00 会 場:第12会場 (G316)
造血細胞分化応答:転写因子ネットワークと代謝による制御と新技術の応用
オーガナイザー:五十嵐 和彦 (東北大学)、伊藤 亜里 (理化学研究所)
講演者・概要▼
講演者:伊藤 亜里 (理化学研究所)、宮崎 正輝 (京都大学)、加藤 浩貴 (東北大学)、矢作 直也 (筑波大学)、綿貫 慎太郎 (国立国際医療研究センター)、鈴木 啓一郎 (大阪大学)
概 要:細胞分化・応答の制御では、転写因子による遺伝情報発現調節がその根幹をなす。転写因子は他転写因子やクロマチン関連タンパク質、代謝物を含めたその上流制御シグナル、そして下流標的遺伝子群から構成されるダイナミックなネットワーク(Gene Regulatory Network, GRN)を形成することで、細胞分化・応答を制御する。造血系細胞分化はGRN研究を先導する細胞システムの一つであり、細胞内代謝、微小環境と生体恒常性の変化やニーズに応じた運命決定と分化進行、そして免疫応答を実現するGRNが解明されつつある。本シンポジウムでは、これらGRNに関する最新の知見を比較して今後の課題を討論するとともに、GRNに関する発見の治療応用、さらなるGRN解明に必要となる新しい技術などを討論する。
1S01a
日 時:11月3日(水)14:50-16:50 会 場:第1会場 (G303+304)
次世代を担う若手研究者が集う疾患糖鎖研究のフロンティア
オーガナイザー:平田 哲也 (岐阜大学)、羽根 正弥 (名古屋大学)
講演者・概要▼
講演者:川西 邦夫 (筑波大学)、大川 祐樹 (大阪国際がんセンター)、郷 詩織 (名古屋大学)、森瀬 譲二 (京都大学)、羽根 正弥 (名古屋大学)、平田 哲也 (岐阜大学)
概 要:全ての細胞表面を覆う糖鎖は、核酸・タンパク質と並ぶ生体高分子であり、多くの重要な生命現象に関与する。糖鎖と疾患との関係は古くから知られており、糖鎖構造の観測、改変を駆使した疾患の理解、制御が長年期待されている。しかし、糖鎖のもつ構造の多様性、複雑性から、現状ではこの期待に十分に応えられていない。一方、これまでの数十年に渡る研究により、糖鎖の生合成を担う糖転移酵素の大部分が同定され、糖鎖生合成の全体像が浮かび上がってきた。糖鎖研究は現在、「生合成の理解」というフェーズから「破綻による疾患の分子機構の理解、克服」のフェーズへと移行しつつあり、糖鎖による疾患の制御が現実味を帯び始めている。本シンポジウムでは、がん、腎疾患、神経疾患と関わりの深い糖鎖修飾、糖脂質研究のこれからを担う6人の若手研究者により、疾患糖鎖研究の現状をご講演いただく。糖鎖による疾患の理解、制御の現在地を確認するとともに、今後の展開を議論する場としたい。
1S02a
日 時:11月3日(水)14:50-16:50 会 場:第2会場 (G404)
神秘の生命物質ポリアミンから探る生命現象と健康への応用
オーガナイザー:植村 武史 (城西大学/京都府立大学)、照井 祐介 (千葉科学大学)
講演者・概要▼
講演者:植村 武史 (城西大学/京都府立大学)、東 恭平 (東京理科大学)、松本 健 (理化学研究所)、柏木 敬子 (千葉科学大学薬学部)、栗原 新 (近畿大学)、照井 祐介 (千葉科学大学)
概 要:ポリアミンはウイルスからヒトまで存在する生命に必須の生理活性アミンである。命の誕生から死まで様々な生命現象の根幹を担う生命物質であり、その機能を解明することによって、生命の神秘が解き明かされると期待されている。また近年、ポリアミン代謝の乱れが様々な疾患と関連することが指摘されており、ポリアミンホメオスタシスの維持が健康長寿に役立つことがわかってきた。 本シンポジウムでは、ポリアミンの生理機能の解析から生命現象を理解し、人々の健康に貢献する最新の研究成果を共有し、ポリアミン研究の今後について議論する。シンポジウムを契機として、新たな共同研究締結の機会を提供したい。
1S04a
日 時:11月3日(水)14:50-16:50 会 場:第4会場 (G402)
動物モデルによる先端がん研究
オーガナイザー:鈴木 聡 (神戸大学)、平尾 敦 (金沢大学)
講演者・概要▼
講演者:西尾 美希 (神戸大学)、平尾 敦 (金沢大学)、中村 卓郎 (がん研・発がん研究部)、山田 泰広 (東京大学)、小玉 尚宏 (大阪大学)、北嶋 俊輔 (がん研・細胞生物部)
概 要:ヒト悪性腫瘍のマウスモデルは、発癌や癌進展の理解や、新しい抗癌剤による治療効果の評価に極めて大切である。本シンポジウムでは、ドライバー遺伝子を変異させることによって、融合遺伝子を発現させることによって、代謝を撹乱することによって、細胞老化を引き起こすことによって、あるいはユニークな変異方法によって、革新的な癌マウスモデルなどを作成・利用した6人の講演者で構成する。本シンポジウムの目的は、新しいマウスモデルを紹介し、発癌や癌進展の生化学的機構や基本原理の理解を深化させること、種々の分子標的薬耐性に重要なシグナル経路を見出すこと、また新しい抗腫瘍薬を開発することなどである。
1S05a
日 時:11月3日(水)14:50-16:50 会 場:第5会場 (G401)
呼吸器疾患研究 - 最近の進展 –
オーガナイザー:粕谷 善俊 (千葉大学)、巽 浩一郎 (千葉大学)
講演者・概要▼
講演者:巽 浩一郎 (千葉大学)、鈴木 拓児 (自治医科大学)、寺田 二郎 (国際医療福祉大学)、重城 喬行 (アムステルダム大学)、粕谷 善俊 (千葉大学)
概 要:COVID-19の世界的猛威は、図らずも呼吸器疾患への関心を高めている。呼吸器は、ガス交換という主たる機能を持ち常に外気と接する特殊な臓器であり、酸素のみでなく、粉塵、オキシダントやSARS-CoV-2などの病原体に晒されている。呼吸器には、このような外敵に対して正常な肺内環境を維持すべく防御・調節機構が備わっているが、その機能破綻が様々な呼吸器疾患を演出する。呼吸器疾患の多くはcommon diseaseであると同時に難治性疾患である。本セッションでは、生化学的基礎研究の臨床領域へのフィードバックを念頭に、特に、肺胞蛋白症、肺胞低換気症候群、肺動脈性肺高血圧症、特発性肺線維症などの呼吸器指定難病の解明と治療に挑む先端研究者による講演を行う。
1S06a
日 時:11月3日(水)14:50-16:50 会 場:第6会場 (G302)
細胞外膜小胞による細胞応答 〜微生物からヒトまで〜
オーガナイザー:野村 暢彦 (1.筑波大学 2.JST )、華山 力成 (金沢大学)
共催:新学術領域研究「超地球生命体を解き明かすポストコッホ機能生態学」・JST CREST/さきがけ「細胞外微粒子」・JST ERATO野村集団微生物制御プロジェクト
講演者・概要▼
講演者:野村 暢彦 (筑波大学/JST )、岡本 章玄 ((国研)物質・材料研究機構)、小嶋 良輔 (東京大学/JSTさきがけ)、吉田 知史 (早稲田大学)、華山 力成 (金沢大学)
概 要:細胞応答は、動物・植物・微生物の全ての生物において、生命現象の重要な共通基盤である。近年、すべての生物界にわたって、脂質二重膜により構成された数十〜数百nmの細胞外膜小胞が報告され注目されている。ヒト・動物においては、エクソソームやマイクロベジクルなどが知られており、免疫応答の制御や癌・神経変性など、様々な疾患への関与が明らかになっている。また、グラム陰性・陽性に関わらず全ての細菌が細胞外小胞(メンブレンベシクル(MV))を産生し、種・属を越えた細菌間のみならず細菌-動物間のMVを介した細胞応答が存在することも明らかになってきた。このように細胞外膜小胞による細胞応答は、動物個体内のみならず、微生物など生物界の壁を超えて注目されている。 本シンポジウムは、ヒト・動物また微生物の細胞外膜小胞を介した細胞応答について、生物界を越えた総合理解の場を提供し、生命ネットワークの理解を深めることを目的とする。
1S07a
日 時:11月3日(水)14:50-16:50 会 場:第7会場 (G301)
シリア-中心体系のダイナミズムと多様な生命現象の制御機構
オーガナイザー:中山 和久 (京都大学)、北川 大樹 (東京大学)
講演者・概要▼
講演者:中山 和久 (京都大学)、小林 哲夫 (奈良先端科学技術大学院大学)、篠原 恭介 (東京農工大学)、上原 亮太 (北海道大学)、北川 大樹 (東京大学)
概 要:シリア-中心体系は細胞周期においてダイナミックに変化する。分裂期の細胞において、中心体は紡錘体形成の中心として細胞分裂を制御するのに対して、静止期の細胞では、中心小体が基底小体となって繊毛(シリア)形成の中心となる。また、シリア-中心体系は、様々な駆動力を発生させる運動性繊毛、および化学的シグナルや機械的シグナルの受容と伝達に関与する一次繊毛が機能するための基盤となり、多様な生命現象を制御する。このように重要な機能を果たすことから、分裂期の中心体の複製や分配、静止期の繊毛形成や繊毛内タンパク質輸送の破綻は、がんや多岐にわたる重篤症状を呈する遺伝性疾患の原因となる。しかし、シリア-中心体系の機能の制御には多くの「ナゾ」が残されている。本シンポジウムでは、多様な生命現象を制御するシリア-中心体系の「ナゾ」に迫るこれまでの研究成果をもとにして、今後のシリア-中心体系研究の展望について熱い議論を交わしたい。
1S08a
日 時:11月3日(水)14:50-16:50 会 場:第8会場 (G312)
生体を造り、支え、そして歪ませる造血システム
オーガナイザー:幸谷 愛 (東海大学)、片山 義雄 (神戸大学)
講演者・概要▼
講演者:片山 義雄 (神戸大学)、加藤 尚志 (早稲田大学)、井上 克枝 (山梨大学)、西山 成 (香川大学)、高橋 裕 (奈良県立医科大学)、佐野 元昭 (慶応義塾大学)
概 要:血球の分化・増殖機構の解明を中心に発展してきた血液学では、その専門性ゆえに生体全体における位置づけや他臓器との相互作用という観点での理解は進まなかった。本領域では、比較生物学と進化医学的観点から造血組織の環境応答とそれに伴う変遷を理解するとともに、臓器の発生や機能維持を神経系や内分泌代謝系と連携しながら造血システムが支える仕組みを明らかにする。さらに造血システムの歪みによって引き起こされる精神疾患・ウイルス感染症と癌・心血管病などの現代病についての疾患生理を解明する。これらの3つのアプローチによって、生体理解の礎となる新たな学問体系「血のチカラ」を築き上げる。
1S09a
日 時:11月3日(水)14:50-16:50 会 場:第9会場 (G313)
創薬を志向したケミカルバイオロジー
オーガナイザー:北 将樹 (名古屋大学 )、鈴木 智大 (宇都宮大学)
共催:新学術領域研究「化学コミュニケーションのフロンティア」
講演者・概要▼
講演者:井貫 晋輔 (京都大学)、井本 正哉 (順天堂大学)、上杉 志成 (京都大学)、舘野 浩章 ((国研)産業技術総合研究所)、田中 良和 (東北大学)
概 要:ケミカルバイオロジーは化学・生化学を含む様々な基幹分野の融合により発展してきた学問であり、ゲノミクス、メタボロミクス、ケモインフォマティックスなどとの協同により、生体内の多様な化学シグナルの統合的な理解が達成されつつある。生物種間で働く化学シグナルを理解し、生物活性リガンドの探索・同定・機能解析ならびに標的指向型表現型スクリーニングの実践により、創薬シーズやケミカルツールの論理的設計など先端医療への応用・展開も期待されている。本シンポジウムでは、天然物および合成リガンドを基軸にして機能性分子の開発を推進する第一線の研究者から講演をいただき、化学シグナルの理解による多様な生物機能の制御の実現や、革新的な医農薬の創出など、創薬を志向したケミカルバイオロジー研究の今後の方向性について議論したい。
1S10a
日 時:11月3日(水)14:50-16:50 会 場:第10会場 (G314)
新興感染症:新型コロナウイルスに即応する生化学~診断・治療・疫学への越境
オーガナイザー:城戸 康年 (大阪市立大学)、中釜 悠 (大阪市立大学)
講演者・概要▼
講演者:北 潔(長崎大学)、松原 三佐子 (大阪市立大学)、EveristeTsibangu (大阪市立大学)、赤畑 渉 (VLP Therapeutics Inc.)、仁田原 裕子 (大阪市立大学)、中釜 悠 (大阪市立大学)
概 要:新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が全地球的な危機となり、科学が果たすべき役割は極めて大きい。破壊的パンデミックとワクチン開発をはじめとした破壊的イノベーションは、従来の学問領域を陳腐化させた。次世代の研究者は既存の学問体系の再構築が求められるが、本シンポジウムでは、COVID-19発生からおよそ2年が経過する時点で、若手研究者が「越境」した足跡をたどり、新興感染症に対する基礎科学の在り方を議論したい。本シンポジウムでは、新興ウイルス感染症においてイノベーションを駆動する宿主免疫応答の理解から開始し、新規血清学的診断の開発や疫学研究、回復者血漿の効率的選別を紹介する。続いて、病期に基づいた分子マーカー探索や新規抗ウイルス薬開発、ワクチン開発について、幅広い専門分野の研究者から講演していただく。さらに、わが国が感染症研究拠点を形成しているアフリカや中米での国際共同研究も紹介する。
1S11a
日 時:11月3日(水)14:50-16:50 会 場:第11会場 (G315)
超硫黄が切り拓く革新的オミックス研究とレドックスバイオロジー
オーガナイザー:澤 智裕 (熊本大学)、有澤 美枝子 (東北大学)
講演者・概要▼
講演者:本橋 ほづみ (東北大学)、西田 基宏 (九州大学)、居原 秀 (大阪府立大学)、赤池 孝章 (東北大学)、澤 智裕 (熊本大学)、梅澤 啓太郎 (東京都健康長寿医療センター研究所)
概 要:硫黄は生体分子の必須素子として、含硫アミノ酸やビタミンなどを構成する重要な機能を担っている。近年、硫黄が直鎖状に連結した超硫黄(supersulfide)を生体が積極的に合成し、そのユニークなレドックスバイオロジーに立脚したエネルギー産生や感染防御、タンパク質品質保持など多彩な生物機能の発現に関わることが明らかとなってきた。超硫黄の生物学的意義の解明には、システイン・グルタチオンパースルフィドなどの低分子超硫黄や、タンパク質中の超硫黄を包括的に解析する超硫黄オミックスや、その微細局在を知るイメージング技術の構築が不可欠である。本シンポジウムでは、超硫黄のレドックスバイオロジーの統合的理解に向けた、革新的定量オミックスとイメージング技術、生体機能、ケミカルモジュレーターの開発や超硫黄オミックスの世界標準に関するコンソーシアムの構築などの集学的なアプローチを議論する。
1S12a
日 時:11月3日(水)14:50-16:50 会 場:第12会場 (G316)
クロマチン構造による遺伝子発現制御機構
オーガナイザー:胡桃坂 仁志 (東京大学 )、立和名 博昭 ((公財)がん研究会がん研究所)
共催:新学術領域研究「遺伝子制御の基盤となるクロマチンポテンシャル」
講演者・概要▼
講演者:胡桃坂 仁志 (東京大学)、立和名 博昭 ((公財)がん研究会がん研究所)、大川 恭行 (九州大学)、佐藤 優子 (東京工業大学)、玉田 洋介 (宇都宮大学)、栗原 美寿々 (北海道大学)
概 要:真核生物において、ゲノムDNAはクロマチン構造を形成している。近年、クロマチン構造が遺伝子発現制御に重要な役割を果たすことが明らかになり、エピジェネティックな遺伝子制御機構として注目されている。クロマチン構造はヒストンとDNAからなるヌクレオソームを基本単位とし、ヌクレオソームが数珠状に連なって形成されている。ヒストンのメチル化やアセチル化などの化学修飾、ヒストン亜種であるヒストンバリアントの有無により、クロマチンは相互作用する因子を変化させることで多様な構造と機能を獲得している。そのため、これらの相互作用因子も含めたクロマチン構造が遺伝子発現制御においてどのように機能するかを明らかにすることが、遺伝子発現制御機構の解明において重要である。本シンポジウムでは、クロマチン構造が遺伝子発現を制御する機構について、原子分解能での構造解析から細胞および個体を用いた最新の研究成果を紹介する。
1S01e
日 時:11月3日(水)17:00-19:00 会 場:第1会場 (G303+304)
多領域に拡がる糖鎖の網羅的生物機能研究の最前線
オーガナイザー:栂谷内 晶 (産業技術総合研究所/創価大学)、佐藤 ちひろ (名古屋大学)
講演者・概要▼
講演者:西原 祥子 (創価大学)、北島 健 (名古屋大学)、藤本 ゆかり (慶應義塾大学)、古川 潤一 (北海道大学)、西山 啓太 (慶應義塾大学)、栂谷内 晶 (産業技術総合研究所/創価大学)
概 要:DNA・タンパク質に次ぐ第3の生命鎖である糖鎖は、タンパク質や脂質に付加されて広く身体に分布し、多様な生命反応に深く関わっている。しかし、その構造や生合成過程は複雑なため、ゲノム研究等と比較して解析が難しく、多くの重要な生命現象における糖鎖の働きが十分に明らかではない。近年、オミクス解析を始めとした様々な技術の導入による糖鎖関連の網羅的データの蓄積、データサイエンス、独自の糖鎖解析技術も加わり、糖鎖の生物機能研究がさらに活発化してきている。このような糖鎖の解析は、基本的生物現象のほか、がんや遺伝性疾患などの疾病はもちろん、生物学・農学・医学のあらゆる領域に及ぶ、生命科学の本質的な問いに答えることに繋がると考えられる。本シンポジウムでは、糖鎖が関わる生命現象の統合的理解を目指す、網羅的解析や独自技術に基づいた糖鎖と他領域との融合研究の最前線を紹介し、今後の糖鎖機能研究の発展を促す場としたい。
1S02e
日 時:11月3日(水)17:00-19:00 会 場:第2会場 (G404)
さきがけ「生体における微粒子の機能と制御」成果報告会~微粒子を追う、捕まえる、操る~
オーガナイザー:中野 明彦 (理化学研究所)、佐藤 健 (群馬大学)
共催:JSTさきがけ「生体における微粒子の機能と制御」
講演者・概要▼
講演者:中野 明彦 (理化学研究所)、佐藤 健 (群馬大学)、井田 大貴 (東北大学 )、今見 考志 (京都大学)、小山 隆太 (東京大学 )、許 岩 (大阪府立大学 )、中江 進 (広島大学 )
概 要:近年、PM2.5やカーボンナノチューブなど環境中の微粒子(外因性微粒子)の生体内への影響や、エクソソームなど生体内で形成された微粒子(内因性微粒子)の機能が注目されています。2017年10月に発足したJSTさきがけ「生体における微粒子の機能と制御」研究領域では、微粒子の体内動態や機能の解明、さらにはそれらの制御に関する研究開発の推進によって、微粒子により惹起される生命現象の本質的な課題に取り組んでいます。今回、第2回成果報告会として、2018年度採択のさきがけ研究者の中から5名の研究者が、さきがけプログラムとして開発した微粒子解析測定技術と微粒子が生体に及ぼす影響とその意義について研究成果を分かり易く紹介します。さきがけ「微粒子」の研究成果を幅広い見地から評価、ご助言いただきますとともに、成果の活用・展開への機会といたしたく、JST共催として開催を希望いたします。
1S03e
日 時:11月3日(水)17:00-19:00 会 場:第3会場 (G403)
躍動するユビキチンコード研究
オーガナイザー:大竹 史明 (星薬科大学)、深井 周也 (京都大学)
共催:新学術領域研究「ケモテクノロジーが拓くユビキチンニューフロンティア」
講演者・概要▼
講演者:深井 周也 (京都大学)、西山 敦哉 (東京大学)、松尾 芳隆 (東北大学)、鐘巻 将人 (国立遺伝学研究所)、佐伯 泰 (東京都医学総合研究所)、大竹 史明 (星薬科大学)
概 要:ユビキチン修飾は生体に必須の翻訳後修飾であり、タンパク質品質管理に加え、シグナル伝達や転写・翻訳、細胞内輸送など多彩な生命現象を調節している。ユビキチン修飾の機能的多様性は異なる形態のユビキチン鎖によって担われており、ユビキチン鎖が内包する機能情報は「ユビキチンコード」と称される。近年、「翻訳調節」や「エピゲノム」、さらには「液-液相分離」など、ユビキチンコードが担う新たな生命現象が続々と明らかになり、ユビキチンコード研究は新たな時代に突入している。本シンポジウムでは、構造生物学やプロテオミクス技術に加え、プロテインノックダウン技術など最新のツールを駆使してユビキチンコードの多彩なバイオロジーに取り組む研究者が集結し、最新の知見を紹介するとともに、ユビキチンコード研究の今後の展開を議論したい。
1S04e
日 時:11月3日(水)17:00-19:00 会 場:第4会場 (G402)
腎臓の疾患と治療から再考する細胞機能
オーガナイザー:淺沼 克彦 (千葉大学)、古市 賢吾 (金沢医科大学)
講演者・概要▼
講演者:山田 浩司 (岡山大学)、牧野 慎市 (千葉大学)、山原 康佑 (滋賀医科大学)、山本 伸也 (京都大学)、豊原 敬文 (東北大学)
概 要:腎臓は老廃物の排泄と生体恒常性維持のために,特殊に分化した細胞群から構成されている.それぞれの細胞は,腎臓の持つ種々の機能を発揮するために,特有の形態や機能を持ち,相互に連関している.近年,様々な解析技術を用いて,腎構成細胞の構造や機能の解析が進み,疾患や治療における新たな知見が集積してきている.特殊性に分化した細胞で得られた知見であるからこそ,得られる知見は他の領域に新たなアイデアをもたらす可能性を有すると考える. 日本腎臓学会では、腎臓研究の裾野を広げることが重要と考えている.日本生化学会・会員の皆様に最近の腎治療および病態解明から得られた細胞の形態や機能に関する新知見を紹介し,腎疾患への興味と研究参加を呼びかける目的で本シンポジウムを企画した.
1S05e
日 時:11月3日(水)17:00-19:00 会 場:第5会場 (G401)
健康長寿社会に向けた和漢薬研究の新展開
オーガナイザー:中川 嘉 (富山大学 )、早川 芳弘 (富山大学)
講演者・概要▼
講演者:早川 芳弘 (富山大学)、東田 千尋 (富山大学)、磯濱 洋一郎 (東京理科大学)、上園 保仁 (東京慈恵会医科大学)
概 要:超高齢化社会を迎えた我が国では様々な病気の患者を増加しており、大きな問題となっている。そのために、新たな治療戦略の構築が必要となっている。本シンポジウムでは、その一つとして、和漢薬に着目する。和漢薬は長い歴史の中で生薬の種類、量、組み合わせなどで作られ、使用されてきた。和漢薬は西洋薬治療で効果を示さない症例でも治療効果が認められ使用される場合や、西洋薬の補完剤としても使用されている。このように、和漢薬の効果は誰もが知るところであるが、科学的根拠が乏しかった。また、和漢薬は複合薬物であるため、作用機構を明確にするのは難しかった。近年、科学技術の向上により、和漢薬に対する基礎研究が進み、分子レベルでの作用機構の解明からその薬効メカニズムが明らかになり、東西医薬学の融合が進んでいる。本シンポジウムでは、健康長寿社会に向けた和漢薬の分子レベルの作用機構から臨床応用について議論したい。
1S06e
日 時:11月3日(水)17:00-19:00 会 場:第6会場 (G302)
学際的研究から切り拓くpH生物学のフロンティア
オーガナイザー:船戸 洋佑 (大阪大学)、栗原 晴子 (琉球大学)
共催:学術変革領域研究(B)「pH応答生物学の創成」
講演者・概要▼
講演者:船戸 洋佑 (大阪大学)、山地 直樹 (岡山大学)、豊福 高志 (海洋研究開発機構)、高橋 重成 (京都大学)、栗原 晴子 (琉球大学)
概 要:pHは全ての生化学反応を左右する最も根源的な要素の一つであり、そのため生体内のpHは極めて厳密に制御されている。一方で生体外の環境pH変動は地球史上かつてない速度で酸性化しているが、この環境pH変動に対する応答・適応機構や他の環境要因との関わりなど、生命とそれを取り巻く環境pHとの関わりについては未開拓の部分が数多く残されている。近年様々な分野において、技術革新や新たな考え方の導入、知見の蓄積などによりこれらの生命とpHに関わる課題にアプローチできる素地が整ってきており、またpHの意外な役割についても次々と明らかとなっている。つまり生命科学におけるpHの理解に「変革」が起こりつつあり、本シンポジウムでは生化学を起点とした、がん、植物、海洋生物学などさまざまな生命科学分野における若手トップランナーを集結させ、pH研究の最先端の成果を紹介、議論する。
1S07e
日 時:11月3日(水)17:00-19:00 会 場:第7会場 (G301)
膜輸送体研究の方法 ~巨人の肩に立ち、輸送体の囁きを聴く~
オーガナイザー:永森 收志 (東京慈恵会医科大学)、阿部 一啓 (名古屋大学)
講演者・概要▼
講演者:高田 龍平 (東京大学)、阿部 一啓 (名古屋大学)、ウイリヤサムクン パッタマ (東京慈恵会医科大学)、李 勇燦 (マックスプランク研究所)、ファンヘルーベ ピーター (ルーヴェン・カトリック大学)
概 要:物質の不均衡は生命の根幹である。膜輸送体(トランスポーター、ポンプ、チャネル)は、膜を隔てた濃度勾配の形成・維持により重要な生理反応に関わり、その機能破綻は疾患の原因となる。近年の解析技術の発展により膜輸送体研究は著しく進展し、注目度は高まっている一方で、500種類以上あるヒトの膜輸送体の多くが機能未知である。よく研究されている膜輸送体は一握りで、そうした分子であってもなお、新たな発見が続いている。生理現象や疾患と関連した膜輸送体の「大きな声」に対する研究は進んでいるが、我々は、膜輸送体の「囁き」に気がついているだろうか。大きな声の影で目立たない「声の小さい」分子に、目を向けているだろうか。R. KabackやG. Sachsら膜輸送体研究を支えてきた「巨人」たち亡き後、我々は彼らの築いた知識の上に立ち膜輸送体をより深く理解しなければならない。過去と現在をつなぎ、新たな知識を築き上げるため、国内外の研究者と膜輸送体を語る。
1S08e
日 時:11月3日(水)17:00-19:00 会 場:第8会場 (G312)
遺伝子改変技術の新展開
オーガナイザー:高橋 智 (筑波大学)、水野 聖哉 (筑波大学)
講演者・概要▼
講演者:小倉 淳郎 (理化学研究所)、依馬 正次 (滋賀医科大学)、高橋 智 (筑波大学)、小林 俊寛 (東京大学)、水野 聖哉 (筑波大学)
概 要:ゲノム編集技術の開発を基盤として、様々な遺伝子改変技術が開発されている。本シンポジウムでは新たな改変技術とその応用例を紹介したい。
1S09e
日 時:11月3日(水)17:00-19:00 会 場:第9会場 (G313)
分子・細胞研究者が挑戦する医療イノベーション
オーガナイザー:高木 淳一 (大阪大学)、保仙 直毅 (大阪大学)
講演者・概要▼
講演者:星野 温 (京都府立医科大学)、酒井 克也 (金沢大学)、保仙 直毅 (大阪大学)、籠谷 勇紀 (愛知県がんセンター研究所)
概 要:臨床医学者と有機化学者、薬理学者などのチームが連携すれば可能であった伝統的な低分子化合物医薬の開発にくらべ、バイオ医薬品や細胞医薬品、遺伝子治療などの先端医療のシーンでは遙かに広い分野の研究者の集結が必要である。また、COVID-19などでは従来とは別次元の医薬品開発スピードが求められ、「医療技術開発」はもはや一部の医学者や製薬企業の仕事ではなく、ライフサイエンス研究者のだれもが当事者として重要な役割を果たし得る時代に突入している。本シンポジウムでは、分子・細胞レベルの基礎的研究に従事していた研究者が、持てる知識と経験を投入して、「予算取りのための方便」ではない真の医療応用につなげようとしている例をいくつか紹介し、基礎研究者主体の本学会からのさらなる新しい医療イノベーション産生を促進したい。
1S10e
日 時:11月3日(水)17:00-19:00 会 場:第10会場 (G314)
SARS-CoV-2の感染・病態におけるウイルス―宿主間相互作用
オーガナイザー:久場 敬司 (秋田大学)、神谷 亘 (群馬大学)
講演者・概要▼
講演者:岩見 慎吾 (名古屋大学)、神谷 亘 (群馬大学)、木戸屋 浩康 (大阪大学)、沢村 達也 (信州大学)、鈴木 忠樹 (国立感染症研究所)、福原 崇介 (北海道大学)、久場 敬司 (秋田大学)
概 要:新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は無症状、軽度の感冒様の症状からICUでの加療を要する重症例や突然死に至るまで幅が広く、回復後の後遺症も大きな問題となっている。患者情報や検体についての大規模な解析や臨床治験が行われているが、パンデミックから1年が経過して決定的な病態を規定する因子や特効薬は見つかっていない。このため学際的なアプローチが不可欠であり、基礎医学分野でもウイルス学、生化学、細胞生物学などから理論数理学に至るまで幅広い研究分野の研究者がCOVID-19の研究に参画している。本シンポジウムでは、SARS-CoV-2感染・病態におけるウイルスと宿主の相互作用の視点から、ウイルスの生態、宿主の免疫炎症応答、血栓・血管炎、感染モデル動物、理論数理学アプローチにおける研究成果をオーバービューし、ポストコロナに向けた新たな異分野融合研究の展開を考える機会としたい。
1S11e
日 時:11月3日(水)17:00-19:00 会 場:第11会場 (G315)
レドックス環境下のオルガネラ対応戦略
オーガナイザー:藤木 幸夫 (九州大学)、潮田 亮 (京都産業大学)
講演者・概要▼
講演者:藤木 幸夫 (九州大学)、潮田 亮 (京都産業大学)、柳 茂 (学習院大学)、関根 弘樹 (東北大学)、久堀 徹 (東京工業大学)、斎藤 芳郎 (東北大学)
概 要:生命は酸素の恩恵を受けつつも、一方で酸素に抗ってきた。このため、細胞は内因性あるいは外因性の酸化ストレスに常に曝されることになるが、細胞内コンパートメントではそれぞれ独自のレドックス環境が構築され、それに対応するための実に巧妙なレドックス制御システムが備わり、生体の恒常性を維持している。近年、オルガネラ独自あるいはオルガネラ間連携を介した非常にユニークな酸化ストレス感知システムや応答戦略が次々と明らかにされており、細胞内恒常性維持の観点からも極めて重要かつ喫緊な研究課題となっている。本シンポジウムでは、異なるレドックス環境下における酸化ストレス感知機構や酸化ストレスに応じた細胞の適応、対抗戦略について最新の知見を踏まえつつ議論したい。
1S12e
日 時:11月3日(水)17:00-19:00 会 場:第12会場 (G316)
ゲノムの構造・機能・安定性に関する研究の新視点
オーガナイザー:保川 清 (京都大学)、上原 了 (愛知県がんセンター研究所)
講演者・概要▼
講演者:板谷 光泰 (信州大学)、大山 隆 (早稲田大学)、津中 康央 (横浜市立大学)、保川 清 (京都大学)、上原 了 (愛知県がんセンター研究所)
概 要:ゲノムを理解することは生命科学の重要テーマである。今日、ゲノムの構造解析には、X線だけでなくクライオ電子顕微鏡やNMRが用いられている。遺伝情報は核DNAの高次構造や物理的特性にも刻まれており、核酸の塩基配列がすべてではない。ゲノムの構造や安定性が遺伝子の機能発現に及ぼす影響を理解することは、生物機能をゲノムレベルで制御する上で重要である。DNA複製の際にはDNAポリメラーゼがリボヌクレオチドを一定の割合でDNA鎖に取り込み、リボヌクレアーゼH2がこれを除去することでゲノムの安定性が維持される。一方では、500 kbp以上のサイズのゲノムが人工的に合成できるシステムが開発された。本シンポジウムではこれらの分野の研究者が最新の話題を提供し、ゲノムの構造・機能・安定性に関する新しい概念についての議論を共有する場としたい。
2S01m
日 時:11月4日(木)9:00-11:00 会 場:第1会場 (G303+304)
脂質生物学の新しいパラダイム
オーガナイザー:村上 誠 (東京大学)、杉本 幸彦 (熊本大学)
講演者・概要▼
講演者:村上 誠 (東京大学)、河野 望 (東京大学)、大石 由美子 (日本医科大学)、森下 英晃 (東京大学/順天堂大学)、遠藤 祐介 (かずさDNA研究所)、杉本 幸彦 (熊本大学)
概 要:脂質は、細胞膜の主要構成要素、最大のエネルギー源、細胞内外で働くシグナル分子、体表バリアの主成分、として生命に必須の根源的物質であり、その質的量的変化は様々な疾患と関連する。かつては生命科学の中で地味な領域であった脂質生化学は、今や代謝・免疫・がん・神経・皮膚・生殖・発生などの病態生理と密接に結びつき、脂質生物学へと大きく発展を遂げた。我が国の脂質生物学は世界の当該研究領域を牽引し、健康志向の高まりから国民の関心も高い。本シンポジウムでは6名の演者を招き、脂質の四大機能を俯瞰した脂質生物学研究の最前線について、最新の話題を提供する。具体的には、細胞外リン脂質代謝酵素sPLA2の新しい動作原理、古くて新しいプロスタグランジンの新機能、NASHに関わるリン脂質と中性脂質の新しいクロストーク、脂質によるT細胞免疫の新規制御機構、脂質がつなぐ炎症―再生連携のメカニズム、細胞内オルガネラ膜の大規模分解などの話題を取り上げる。
2S02m
日 時:11月4日(木)9:00-11:00 会 場:第2会場 (G404)
遺伝子制御の新世界
オーガナイザー:鈴木 洋 (名古屋大学)、森田 剣 (ハーバード大学)
講演者・概要▼
講演者:野島 孝之 (オックスフォード大学)、鈴木 洋 (名古屋大学)、河口 理紗 (コールドスプリングハーバー研究所)、嶋田 健一 (ハーバード大学)、森田 剣 (ハーバード大学)、青井 勇樹 (ノースウェスタン大学)
概 要:遺伝子の制御は生命現象の根幹をなしますが、その基本的なメカニズムの理解は今もアップデートされ続けています。バイオインフォマティクス・次世代シーケンサー・ゲノム編集・シングルセル解析などの技術躍進は、このような遺伝子制御の高解像度の理解を深めるだけでなく、ゲノム情報と疾患メカニズム、ヒト集団とシングルセルでの遺伝子制御といったアプローチの異なる大きく離れた情報群を連続的に統合し、高次生命システムの本質に迫る新たな研究の潮流を生み出しています。本シンポジウムでは、コロナ禍での新しい学会スタイルの1つとして、留学後・留学中の研究者をつなぎ(ジェットラグ on time シンポジウム)、遺伝子制御・遺伝子ネットワーク研究の最先端と未来について幅広く議論します。
2S03m
日 時:11月4日(木)9:00-11:00 会 場:第3会場 (G403)
先端生命科学技術による生命現象の理解と制御
オーガナイザー:吉原 栄治 (ランドキスト研究所/カリフォルニア大学)
講演者・概要▼
講演者:吉原 栄治 (ランドキスト研究所/カリフォルニア大学)、高橋 悠太 (ソーク研究所)、原 敏朗 (ブロード研究所)、小栗 靖生 (ハーバード大学)
概 要:生命科学技術の発展により複雑な生命現象の解析が可能になり、得られた知見による医療への応用が期待されている。本セッションはジェットラグシンポジウムの一環として、米国で活躍する若手研究者を迎え最先端生命科学技術とその応用に関する最新の研究成果について討論する。新たなアプローチによる、幹細胞、ゲノム編集、シングルセル遺伝子発現解析、マウスの個体を用いた生理学等に関する重要な課題への挑戦を紹介する。
2S04m
日 時:11月4日(木)9:00-11:00 会 場:第4会場 (G402)
造血細胞、エクソソーム、多階層オミクス解析からみる全身性疾患生物学
オーガナイザー:星野 歩子 (東京工業大学 )、井上 大地 (神戸医療産業都市推進機構)
講演者・概要▼
講演者:佐野 宗一 (バージニア大学)、橋本 彩子 (東京工業大学)、指田 吾郎 (熊本大学)、大澤 毅 (東京大学)、脇田 将裕 (大阪大学)、井上 大地 (神戸医療産業都市推進機構)
概 要:生命誕生前の妊娠がもたらす合併症から、加齢や老化を背景とする「がん」に至るまで、各臓器レベルでの炎症・ストレス・代謝異常・遺伝子発現異常に端を発して、臓器横断的に影響を及ぼすことが明らかとなりつつある。このような現象を新しい手法により可視化し、全身性の異常を多角的に理解することは病態の正しい理解と治療法の開発において不可欠な課題といえる。 本シンポジウムでは、妊娠・老化・がん・動脈硬化等が進展する上で、あらゆる臓器で生じる変化、特にそれを司る様々な循環代謝物・炎症性分子・血液細胞・エクソソームなどに着目した研究およびその解析方法についての統合的な理解を目標とする。「全身性疾患生物学」をテーマに、予想もしない臓器連関、そのメディエーターやエフェクターの同定、メカニズムに基づく治療アプローチについて、各分野で活躍する気鋭の若手研究者を演者に迎え、未来志向の新しい生物学を議論する。
2S05m
日 時:11月4日(木)9:00-11:00 会 場:第5会場 (G401)
がん治療に直結する最新複製制御機構
オーガナイザー:東山 繁樹 (愛媛大学)、村井 純子 (慶應義塾大学)
講演者・概要▼
講演者:村井 純子 (慶應義塾大学)、西谷 秀男 (兵庫県立大学)、塩谷 文章 (国立がん研究センター研究所)、前川 大志 (愛媛大学)、大橋 紹宏 (国立がん研究センター)
概 要:DNA複製は、複製開始点の発火に引き続く複製フォークの伸長であり、厳密なタイミングと再複製回避の複雑な制御機構で成り立つ。無限増殖するがん細胞を制圧するために、DNA複製を阻止する戦略は、古くからDNA障害型抗がん剤やDNA複製阻害剤で実行されてきた。本シンポジウムでは複製制御因子の最新の知見をもとに、複製制御の視点から新たな抗がん戦略を議論する。主な内容は、複製開始の必須タンパク質CDT 1の新規制御機構、DNAヘリカーゼMCMのリン酸化酵素CDC 7を阻害することによる複製開始抑制の抗がん効果、そしてDNA障害型抗がん剤の抗がん効果を飛躍的に高めるSLFN 11による複製制御機構について、最新知見の紹介を予定している。またその他の複製制御因子のdruggability についても議論したい。
2S06m
日 時:11月4日(木)9:00-11:00 会 場:第6会場 (G302)
新たな力で切り開くミトコンドリア品質管理機構の新展開
オーガナイザー:柳 茂 (学習院大学)、岡 敏彦 (立教大学)
講演者・概要▼
講演者:椎葉 一心 (学習院大学)、赤羽 しおり (立教大学)、奥野 龍禎 (大阪大学)、山下 俊一 (新潟大学)、小谷 哲也 (東京工業大学)
概 要:ミトコンドリアは細胞のエネルギー通貨であるATPを産生するだけではなく、脂質代謝、細胞内カルシウムの恒常性維持、免疫応答の調節など多彩な役割を担っている。一方で、ミトコンドリアは常にストレスに曝されているオルガネラであり、酸化的リン酸化反応の過程で発生する活性酸素種(ROS)は、 DNA、脂質、タンパク質を酸化することにより、様々な老化関連疾患の原因になることが報告されている。特に、損傷を受けたミトコンドリアはさらなる ROS の発生を誘発し、細胞全体の劣化を引き起こすと考えられる。 近年、このような細胞にとって有害となる不良ミトコンドリアを選択的に排除するメカニズムがわかってきた。 本シンポジウムでは、ミトコンドリア品質管理機構について精力的に解析を進めてきた研究グループを結集して、新たに明らかになったミトコンドリアの品質管理機構を紹介していただき、病態との関連について議論する予定である。また、今回は若手研究者を中心に発表してもらう予定である。
2S07m
日 時:11月4日(木)9:00-11:00 会 場:第7会場 (G301)
多面的ミトコンドリア機能による生命機能制御
オーガナイザー:魏 范研 (東北大学)、関根 史織 (ピッツバーグ大学)
講演者・概要▼
講演者:富田 野乃 (東京大学)、平林 祐介 (東京大学)、鈴木 純二 (カルフォルニア大学)、田村 康 (山形大学)、関根 史織 (ピッツバーグ大学)、松本 俊介 (九州大学)
概 要:細胞内寄生細菌を祖先とするミトコンドリアはATP産生のみならず実に多様な機能を有し、細胞にとって必要不可欠なオルガネラへと進化した。近年新たな研究手法により、ミトコンドリアが自身の機能を保つ仕組みの詳細が解明されるとともに、細胞の生を支える上で、他のオルガネラとの機能連携の重要性も明らかとなってきた。例えば、ミトコンドリアが持つ独自のタンパク質翻訳系やタンパク質品質管理を制御する装置はミトコンドリアはもとより細胞全体のプロテオスタシス維持に寄与する。ミトコンドリア膜上に存在するイオントランスポーターは、細胞内イオンバランスやシグナル伝達を調節する。ミトコンドリアと小胞体の間ではイオンや膜脂質成分がやりとりされ互いのオルガネラ機能に影響を及ぼす。このように、ミトコンドリア機能の分子基盤の開拓が突破口となり、新しいミトコンドリア生命科学研究が切り開かようとしている。本シンポジウムはミトコンドリア多様性をキーワードに新時代のミトコンドリア研究を支える研究者を招き、多面的な議論を深めたい。
2S08m
日 時:11月4日(木)9:00-11:00 会 場:第8会場 (G312)
冬眠様の能動的低代謝状態における生体の適応機構
オーガナイザー:櫻井 武 (筑波大学)、金 尚宏 (東京大学)
講演者・概要▼
講演者:櫻井 武 (筑波大学)、砂川 玄志郎 (理化学研究所)、金 尚宏 (東京大学 大学院理学系研究科 生物科学専攻)、平野 有沙 (筑波大学)
概 要:一部の哺乳類は冬季などに飢餓から生き延びるため基礎代謝を低下させるために低体温を維持し、エネルギーを節約する生存戦略をとる。冬眠と呼ばれる状態である。冬眠中の動物は非活動状態となり基礎代謝が低下し、種々の生命機能は大幅に低活動になり、その状態がしばらく維持され何らの障害なく回復(復温)する。このメカニズムは生理学的にも非常に興味深いものの、冬眠動物そのものを使用しなければ研究ができないため、研究の進展が妨げられていた。最近、マウスの視床下部の一部の小領域に存在する神経を特異的に興奮させるとマウスの体温が数日間に渡って大きく低下し併せて代謝も著しく低下することがしめされた。この状態は様々な点で冬眠動物にみられる冬眠に酷似していた。この発見は体温制御・代謝制御の新たな機構の発見という生物学的に大きな意義をもつだけではなく、ヒトの人工冬眠が現実味を帯びてくることを示したものである。また、冬眠様状態をマウスを用いて生理的・生化学状態を検討することが可能になった。本シンポジウムでは低体温状態での生理的状態について体内時計や体温制御メカニズムを中心に議論したい。
2S09m
日 時:11月4日(木)9:00-11:00 会 場:第9会場 (G313)
アーキア生化学の最前線
オーガナイザー:石野 良純 (九州大学 )、跡見 晴幸 (京都大学)
講演者・概要▼
講演者:跡見 晴幸 (京都大学)、石野 良純 (九州大学)、Qunxin She (Shandong University)、村上 勝彦 (ペンシルベニア州立大学)
概 要:地球上に生息する生物は3つのドメインに分類される。そのうち、アーキアは極限環境で生息できるものが多く、バクテリアや真核生物には見られない固有の生命機能を有する。メタゲノム解析が盛んになり、アーキアは地球上に広く生息し、系統的に異なるアーキアが次々に提唱されている。本シンポジウムではアーキアの遺伝情報系、細胞構造、エネルギー代謝系、生体防御系(CRISPR/Cas系)などの最前線の生化学を紹介することにより、アーキアの生命現象の理解を深めたい。
2S10m
日 時:11月4日(木)9:00-11:00 会 場:第10会場 (G404)
脳におけるクロマチン制御
オーガナイザー:岩瀬 茂樹 (ミシガン大学)、Dus Monica (ミシガン大学)
講演者・概要▼
講演者:岩瀬 茂樹 (ミシガン大学)、Dus Monica (ミシガン大学)、Stroud Hume (テキサス大学サウスウェスタン校)、Korb Erica (ペンシルベニア大学)
概 要:近年、多くの神経疾患がクロマチンの異常に起因することが分かってきた。しかし、なぜ脳がクロマチンの異常に、より敏感なのかは不明である。脳におけるクロマチン制御はほかの組織と根本的に異なっていることが考えられる。本シンポジウムでは、この分野での専門家が、脳特異的なクロマチンの制御に関する最近の知見を紹介する。
2S11m
日 時:11月4日(木)9:00-11:00 会 場:第11会場 (G315)
低酸素シグナルが炙り出す間質組織の多彩な役割
オーガナイザー:鈴木 教郎 (東北大学)、武田 憲彦 (自治医科大学)
講演者・概要▼
講演者:鈴木 教郎 (東北大学)、田久保 圭誉 (国立国際医療研究センター研究所)、原田 浩 (京都大学)、冨田 修平 (大阪市立大学)、武田 憲彦 (自治医科大学)
概 要:各臓器は、臓器固有の機能を司る実質組織に加え、実質細胞の間隙を埋める間質組織で構成される。従来の臓器機能研究では、実質組織が主役であり、間質組織の役割は、代謝物交換・損傷治癒・感染防御・構造支持などの実質組織の補助に限定されると捉えられてきた。しかし最近の研究から、間質組織の多彩な機能が次々と同定され、担当する実質組織の機能を積極的に制御するだけでなく、液性因子の分泌などを通して、全身の生体調節系に直接作用することもわかってきた。本シンポジウムでは、心臓、腎臓、骨髄および固形腫瘍を例として、間質組織が主役となる生体調節機構とその変容による分子病態の最新知見を紹介する。とくに、間質組織は酸素環境を監視することにより、実質組織および全身の代謝状態を把握しているというアイデアに基づき、低酸素状態を感知した間質組織が引き起こす代謝応答・炎症・細胞分化などの生体応答機構を中心に議論を展開する。
2S12m
日 時:11月4日(木)9:00-11:00 会 場:第12会場 (G316)
温故知新;古くて新しいGATA 転写因子研究の最前線
オーガナイザー:南 敬 (熊本大学)、鈴木 未来子 (東北大学)
講演者・概要▼
講演者:伊藤 悦朗 (弘前大学)、神吉 康晴 (東京大学)、高井 淳 (東北医科薬科大学)、森本 達也 (静岡県立大学)、鈴木 未来子 (東北大学)
概 要:GATA ファミリーは高度に保存された二つのジンクフィンガードメインを有する古くから知られる転写因子で哺乳類では GATA1-6 まで6種類存在する。近年の複合体・Multi-omics 解析の進歩に伴い、これら GATA 転写因子群は単に DNA 配列を認識するだけでなく、遠位エンハンサーとプロモーターの相互作用や他のタンパクとの相互作用を介して、エピゲノム変化を含めた広範な制御に不可欠なものとして再認識されている。更にこれら高次ゲノム制御を介して、GATA 転写因子は従来から知られる初期発生・分化に必須な因子としての位置付けだけでなく、炎症や血管新生まで生体の様々なライフステージや病態に重要な因子として考えられている。そこで本シンポジウムではこれら GATA 転写因子群の新たな切り口を捉え研究を進めている各研究者からの講演を交えて、生化学的基盤概念からの転写制御と病態生理について考えていきたい。
2S01a
日 時:11月4日(木)14:50-16:50 会 場:第1会場 (G303+304)
メタボリックシンドロームにおける脂質代謝研究の最前線
オーガナイザー:松坂 賢 (筑波大学)、小濱 孝士 (昭和大学)
共催:日本動脈硬化学会
講演者・概要▼
講演者:蔵野 信 (東京大学)、小濱 孝士 (昭和大学)、垣野 明美 (信州大学)、藤坂 志帆 (富山大学)、松坂 賢 (筑波大学)
概 要:メタボリックシンドロームは肥満とインスリン抵抗性を背景として、高血糖、脂質代謝異常、高血圧症が共存する病態であり、動脈硬化を相乗的かつ急速に進行させ心血管イベントのリスクを高めることから、その病態解明と有効な治療法の開発が求められている。そのためには、メタボリックシンドロームの基本となる脂質代謝機構の解明に新しい視点から取り組み、その制御法を開発することが重要である。近年の脂質代謝研究は、代謝酵素の同定や質量分析技術の飛躍的な進歩により、新たな代謝制御機構の解明や治療法開発につながるものとして注目を集めている。そこで本シンポジウムでは、様々な視点からメタボリックシンドロームおよび動脈硬化症に関連する脂質代謝研究を取り上げ、最先端の研究成果を紹介して頂くとともに、将来への展望を含めて議論する機会としたい。
2S02a
日 時:11月4日(木)14:50-16:50 会 場:第2会場 (G404)
データ駆動科学エクスプロージョン
オーガナイザー:島村 徹平 (名古屋大学)、大澤 毅 (東京大学)
講演者・概要▼
講演者:太田 禎生 (東京大学)、片岡 圭亮 (慶應義塾大学)、白石 友一 (国立がん研究センター)、島村 徹平 (名古屋大学)
概 要:次世代シークエンサー、質量分析機、イメージングなどの技術革命が進み、膨大な多階層の生命情報が指数関数的に増えているが、多くの生命科学者がその解析に悩まされている。こうした膨大なデータを活用して、既知の学問を超えて革新的な知見・知識を創出するためには、数理科学、情報学、物理学など、異分野で培われた叡智や新たな理論を利活用した異分野融合研究が必要不可欠である。その一方で、分野を跨いで研究するにはどうすればよいか、具体的に何をすればいいのかなど、未だに敷居が高いと感じる生命科学研究者も多いのではないだろうか。本シンポジウムでは、がん、神経科学などの生命現象を、マルチオミクス解析、AI、イメージングなどの最新解析技術でアプローチしている新進気鋭のデータ駆動科学研究者が集まり、最新計測技術や解析技術を紹介する。また、融合研究の魅力を紹介し、若手研究の新規参入のきっかけを提供する。
2S03a
日 時:11月4日(木)14:50-16:50 会 場:第3会場 (G403)
プロテオスタシスを維持するネットワーク経路
オーガナイザー:中井 彰 (山口大学)、徳永 文稔 (大阪市立大学)
講演者・概要▼
講演者:及川 大輔 (大阪市立大学)、小瀬 真吾 (理化学研究所)、村田 茂穂 (東京大学)、武川 睦寛 (東京大学)、遠藤 彬則 (東京都医学総合研究所)、藤本 充章 (山口大学)
概 要:細胞は多くの種類からなるタンパク質群を個別のコンパートメントに含んでいる。これらの細胞内タンパク質を正しい構造と生理的な量に保つこと、つまりプロテオスタシスを維持することは正しい細胞機能に必須である。プロテオスタシスはタンパク質の合成、フォールディング、分解、そして局在などの調節で維持される。その破綻は細胞内に凝集体やアミロイド線維の蓄積を招き、神経変性疾患やがんと密接に関連する。本シンポジウムでは、タンパク質凝集体へ対処するための主要な過程であるシャペロン系とユビキチンープロテアソーム系の細胞内移動を含む調節機構、およびそれらを制御するシグナル伝達と転写調節の分子機構を紹介する。さらに、タンパク質凝集体形成と密接に関連する新規のシグナル伝達や過程も紹介することで、プロテオスタシス調節のネットワーク経路について包括的理解を目指して議論する。
2S04a
日 時:11月4日(木)14:50-16:50 会 場:第4会場 (G402)
生体内におけるグリケーションの役割と食品におけるメイラード反応の意義
オーガナイザー:新井 誠 (東京都医学総合研究所 )、大畑 素子 (日本大学)
講演者・概要▼
講演者:大畑 素子 (日本大学)、新井 誠 (東京都医学総合研究所)、林 泰資 (ノートルダム清心女子大学)、瀬戸山 央 (神奈川県立産業技術総合研究所)、小笠原 裕樹 (明治薬科大学)、棟居 聖一 (金沢大学)、山崎 修道 (東京都医学総合研究所)
概 要:食品科学分野におけるメイラード反応を軸とした研究は、従来、メイラード反応のメカニズムから褐変や香気の生成をコントロールし、食品の品質や嗜好性を向上させることを大きな目的として発展を遂げてきました。そのなかで、近年、メイラード反応生成物の機能性や香気成分による生理作用などの研究が再び注目されています。一方、疾患生物学の領域では、後期ライフステージに共通するリスク因子として、糖尿病や心血管障害などを対象とした研究が盛んに行われてきましたが、近年ではメンタルヘルスの分野でも注目されつつあります。特に、大規模出生コホートによる発達疫学研究からは、精神的不調がグリケーションと関連することも見出されています。本シンポジウムでは、食品科学と疾患生物学の異分野領域の視点から、社会還元につながる新たな発見を共有する場となることを期待しています。
2S05a
日 時:11月4日(木)14:50-16:50 会 場:第5会場 (G401)
血管・リンパ管による生体恒常性維持とその破綻がもたらす病態
オーガナイザー:福原 茂朋 (日本医科大学 )、伊東 史子 (東京薬科大学)
講演者・概要▼
講演者:高倉 伸幸 (大阪大学)、中岡 良和 (国立循環器病研究センター)、築地 長治 (山梨大学)、姜 秀辰 (大阪大学)、伊東 史子 (東京薬科大学)、山本 清威 (日本医科大学)
概 要:全身を張り巡らす血管・リンパ管は、生命維持に必須の器官である。血管は全ての細胞に酸素や栄養を供給するとともに、環境に応じで種々のシグナル分子を産生し組織・臓器の形成・再生・維持に寄与している。そのため、血管機能の破綻は多様な疾患の発症・進展と密接に関連する。特に、現在世界中で猛威を振るうCOVID-19の重症化にも血管が中心的な役割を担うことが報告され、血管研究の重要性が再認識されている。また、リンパ管は組織液の排出、免疫細胞の輸送を制御することで生体恒常性を維持する一方、がんなど種々の疾患の病態にも密接に関連する。近年、これら脈管系についての研究が精力的になされ、生体組織の恒常性維持機構およびその破綻に起因する疾患の発症機構の理解が深まってきた。本シンポジウムでは、本分野をリードする研究者に最新の研究成果をご紹介頂き、今後の血管・リンパ管研究の展開について議論したい。
2S06a
日 時:11月4日(木)14:50-16:50 会 場:第6会場 (G302)
革新的解析技術で迫る膜輸送タンパク質の実像
オーガナイザー:川崎 寿 (東京大学)、中山 義敬 (ビクター・チャン心臓病研究所)
講演者・概要▼
講演者:中山 義敬 (ビクター・チャン心臓病研究所)、Reddy Bharat (シカゴ大学)、篠田 恵子 (東京大学)、久保 彩 (オクラホマ州立大学)、山本 大輔 (福岡大学)
概 要:膜輸送タンパク質は、生体膜を横切る物質輸送を担い、栄養素の取り込み、不要物質の排出、呼吸や光合成によるエネルギー生産、環境応答、シグナル伝達など生命に必須の活動に関わる。膜輸送タンパク質は膜内在性であるため、その解析には可溶性タンパク質と異なる方法が必要となる。本シンポジウムでは、クライオ電子顕微鏡、高速原子間力顕微鏡、スーパーコンピューターを活用した多原子・全原子MDシミュレーション、電気生理学的手法、イメージング技術などの革新的な解析技術を適用して膜輸送タンパク質のこれまで知られていなかった実像(作動原理、動的挙動、生理機能など)に迫る成果を紹介する。紹介する技術は汎用性が高いため、膜輸送研究者が多数在籍する日本生化学会の大会における本シンポジウムの開催は、この分野のさらなる発展に寄与することが期待できる。また年齢、性別、キャリアにおいて多様な講演者で本シンポジウムは構成されている。
2S07a
日 時:11月4日(木)14:50-16:50 会 場:第7会場 (G301)
多細胞システムを支える細胞外環境ダイナミクス
オーガナイザー:藤原 裕展 (理化学研究所)、高田 慎治 (基礎生物学研究所)
講演者・概要▼
講演者:松林 完 (キングス・カレッジ・ロンドン)、平島 剛志 (京都大学)、星野 歩子 (東京工業大学)、高田 慎治 (基礎生物学研究所)、藤原 裕展 (理化学研究所)
概 要:器官は個々の細胞の単なる総和ではなく、多様な細胞とそれが働く「場」としての「細胞外環境」とが一体となって機能する多細胞システムである。細胞外環境には細胞の機能を制御する様々な情報が存在するが、技術的な難しさなどのため、細胞種ごとに最適化された微小環境の分子実体や、細胞との相互作用の時空間ダイナミクスに関する理解は十分ではなかった。しかし近年、細胞外因子の検出・可視化・操作技術などの進展により、細胞外マトリックス、モルフォゲン、エクソソームなどの組織内での動態や活性変化が活写されるようになってきた。その結果、細胞外因子の動態や機能に関する定説を覆すような発見が相次ぎ、古典的概念がアップデートされてきている。本シンポジウムでは、細胞と細胞外環境との相互作用のダイナミクスに関わる最新の研究を紹介し、細胞外環境研究の今後の展開について議論したい。
2S08a
日 時:11月4日(木)14:50-16:50 会 場:第8会場 (G312)
概日時計と病気・老化
オーガナイザー:中畑 泰和 (長崎大学)、深田 吉孝 (東京大学)
講演者・概要▼
講演者:小柳 悟 (九州大学)、中畑 泰和 (長崎大学)、廣田 毅 (名古屋大学)、吉種 光 (東京大学)、Thomas Mortimer (IRB Barcelona)
概 要:生体内のさまざまな生理機能は日内変化するが、その多くは内在性の概日時計によって制御されていることが知られている。概日時計は胚発生後期から時を刻み始め、生後、成熟を経て加齢とともに衰えていく。これまでの疫学調査や動物実験より、正確で頑強な概日時計の維持は、健康促進に働き、健康寿命延長に貢献することが示唆されている。しかし、分子レベルでの概日時計と病気・老化の関連の多くはわかっていない。本シンポジウムでは、概日時計の分子基盤、特に、病気や老化との関連性について最新の生化学・分子生物学・薬理学知見などを紹介し、統合的な概日時計制御の観点から健康寿命延長について議論したい。
2S09a
日 時:11月4日(木)14:50-16:50 会 場:第9会場 (G313)
生理活性ペプチドと中分子創薬〜新たな創薬ブレイクスルーを目指して
オーガナイザー:向井 秀仁 (長浜バイオ大学)、野村 渉 (広島大学)
講演者・概要▼
講演者:野村 渉 (広島大学)、鎌田 瑠泉 (北海道大学)、後藤 佑樹 (東京大学)、大石 真也 (京都薬科大学)、門之園 哲哉 (東京工業大学)、佐藤 伸一 (東北大学)、向井 秀仁 (長浜バイオ大学)
概 要:近年の創薬研究において、そのターゲットとして中分子量の生命分子、すなわちペプチドやオリゴヌクレオチドならびに複合脂質などが新しいモダリティーとして注目されています。なかでもペプチドは、生体内での様々な情報のやりとりにおいて中心的役割を果たしており、多様な難治性疾患や原因不明の病態とも深く関わっていることが明らかになりつつあります。このため、このような難治性疾患の治療を目指したペプチド創薬が近年注目を浴びるようになっています。しかしながら、現実の研究開発現場では、ペプチドの存在意義や生理活性の多様性、さらにはペプチドを取り扱う上での特殊性等に関する認識や情報共有が乏しく、研究・開発を進めるにあたって、しばしば困難に直面するのが現状です。 そこで本シンポジウムでは、中分子創薬としてのペプチドの高い可能性を、基礎研究から技術研究までを含め、研究を牽引する研究者により多面的にご紹介していただくとともに、このシンポジウムにおける研究交流を通じて、国際的見地から日本の中分子創薬研究の振興につなげることを目的とします。
2S10a
日 時:11月4日(木)14:50-16:50 会 場:第10会場 (G314)
神経系の老化・病態における多細胞連携のメカニズム
オーガナイザー:長谷川 潤 (神戸薬科大学)、水谷 健一 (神戸学院大学)
講演者・概要▼
講演者:鶴田 文憲 (筑波大学)、瀬木(西田) 恵里 (東京理科大学)、石原 康宏 (広島大学)、水谷 健一 (神戸学院大学)、長谷川 潤 (神戸薬科大学)
概 要:発達や加齢、外傷・疾患などに伴う神経系の形態的・機能的変化は、神経細胞の他、グリア細胞や免疫細胞など多彩な細胞種の相互作用により引き起こされる。これらの多様な細胞種は直接または間接的な分子コミュニケーションにより、相互に機能や分化調節を制御している。近年の分子生物学的手法やイメージング技術の進歩は、これまで見えていなかった新しい細胞種間コミュニケーションの機構を明らかにしつつある。本シンポジウムでは、老化や疾患による神経系の変化において、多様な細胞種がどのように相互作用し、組織の形態や機能の変化を制御しているのかに関して、最先端の研究成果をご紹介いただくことで、神経系における新たな多細胞間連携について議論する場を提供したい。
2S11a
日 時:11月4日(木)14:50-16:50 会 場:第11会場 (G315)
含硫化合物・温故知新~生物多様性に学ぶ含硫代謝物の多彩な生理機能
オーガナイザー:山本 雄広 (慶應義塾大学 )、辻田 忠志 (佐賀大学)
講演者・概要▼
講演者:山本 雄広 (慶應義塾大学)、辻田 忠志 (佐賀大学)、水沼 正樹 (広島大学)、清水 隆之 (東京大学)、浅野 敦之 (筑波大学)、生田 哲朗 ((国研)海洋研究開発機構)
概 要:硫黄は酸素に乏しい極限環境下にある太古の昔から化学エネルギー合成の材料として利用されてきた。近年の代謝解析研究の隆盛により含硫化合物はバクテリアから哺乳類に至るまで、生殖・発生、老化と寿命、遺伝子発現調節、解毒、ストレス応答、共生関係の成立等様々な生理機能があることが分かってきたものの、その作用機序および制御メカニズムなど依然不明な点が多い。本シンポジウムではさまざまな生物種を研究対象にされている演者に含硫代謝物研究に関する最新の話題を提供してもらうことで様々な生物における「硫黄」の利用のされ方に学び、その普遍性と特殊性について考える機会とし、「古くて新しい」含硫化合物が及ぼす多彩な生理作用について議論したい。
2S12a
日 時:11月4日(木)14:50-16:50 会 場:第12会場 (G316)
染色体の多様な機能を支えるタンパク質高次複合体
オーガナイザー:高橋 達郎 (九州大学)、村山 泰斗 (国立遺伝学研究所)
講演者・概要▼
講演者:正井 久雄 (東京都医学総合研究所)、片山 勉 (九州大学)、角井 康貢 (早稲田大学)、古郡 麻子 (大阪大学)、野澤 佳世 (東京大学)、沖 啓輔 (九州大学)、村山 泰斗 (国立遺伝学研究所)、高橋 達郎 (九州大学)
概 要:遺伝情報の担い手である染色体はDNAと多数のタンパク質からなる巨大かつ複雑な構造体であり、その複製、安定維持や継承反応は、必要に応じて形成、構造変換、解体されるタンパク質高次複合体のはたらきに支えられている。したがって、それらタンパク質高次複合体の機能、構造、制御の解明は、染色体の多様な機能とその制御を理解するための必須の土台と言える。またこのようなタンパク質高次複合体の動態は、実に巧妙かつダイナミズムに富むものであり、最先端の構造解析技術や独創的な分子解析法を用いることにより、初めてその本質を見出すことができるものである。本シンポジウムでは、複製、転写、修復から染色体構築、分配までの広い分野で、また細菌、古細菌、真核生物という三つのドメインにわたって、染色体機能の研究者に最先端の話題を提供して頂き、進化的な視点も含めた広い視野から染色体機能を支えるメカニズムを議論する場としたい。
2S01e
日 時:11月4日(木)17:00-19:00 会 場:第1会場 (G303+304)
スフィンゴ脂質多機能性の新展開
オーガナイザー:木原 章雄 (北海道大学)、沖野 望 (九州大学)
講演者・概要▼
講演者:木原 章雄 (北海道大学)、長野 稔 (立命館大学)、山崎 晶 (大阪大学)、井ノ口 仁一 (東北医科薬科大学)、沖野 望 (九州大学)
概 要:生体膜を構成する脂質の中でもスフィンゴ脂質は多様性と多機能性に富んでいる。本シンポジウムでは,様々な生物種(細菌,植物,哺乳類)におけるスフィンゴ脂質の多様性,生合成,生理機能,病態との関連について最近の研究の新展開について取り上げる。これらには細菌におけるグルクロノシルセラミドとガラクトシルセラミド,植物におけるグルコシルセラミドとイノシトール含有スフィンゴ脂質,哺乳類におけるグルコシルセラミド,ガラクトシルセラミド,ガングリオシド,セラミドが含まれる。これらのスフィンゴ脂質は免疫,環境応答,糖代謝調節,皮膚バリア,神経機能などの生理機能を有し,その生合成異常または恒常性の破綻は様々な病態(肥満/メタボシックシンドローム,自己免疫疾患,神経疾患,皮膚魚鱗癬)を引き起こす。
2S02e
日 時:11月4日(木)17:00-19:00 会 場:第2会場 (G314)
遺伝子発現制御から探る神経発生メカニズム
オーガナイザー:古川 貴久 (大阪大学 )、山本 亘彦 (大阪大学)
講演者・概要▼
講演者:中島 欽一 (九州大学)、古川 貴久 (大阪大学)、花嶋 かりな (早稲田大学)、仲嶋 一範 (慶應大学)、山本 亘彦 (大阪大学)
概 要:中枢神経系の発生・発達過程においては、非常に多様な種類の神経細胞が生み出される。例えば、脊椎動物の網膜においては、大まかには5種類の主要な神経細胞(視細胞、双極細胞、水平細胞、アマクリン細胞、神経節細胞)が存在するが、それぞれの神経細胞はサブタイプに分かれ、マウス網膜でも全体として80種類以上ものサブタイプが知られている。大脳でも同様に神経細胞は多様性に富んでいる。このような多種多様な神経細胞が適切に発生してくるためには、内在的な転写調節因子の発現調節、ならびに細胞外環境からのシグナルが重要な役割を演じていることが示唆されているが、いまだ不明な点が多い。また、細胞分化は当初想定されていた以上に長期に及び、生後の外界からの影響によっても、遺伝子発現調節を介して分化が制御されるが、そのメカニズムも興味深い。さらに、それをコントロールすることによって、神経再生や精神神経疾患の治療法の基盤となる知見にも繋がることが期待されている。本シンポジウムでは、遺伝子発現制御の観点から神経発生機構について研究されている研究者に御講演いただき、古くて新しい神経発生における遺伝子発現制御の問題について理解を深めたい。
2S03e
日 時:11月4日(木)17:00-19:00 会 場:第3会場 (G403)
選択的オートファジー
オーガナイザー:小松 雅明 (順天堂大学)、池田 史代 (九州大学)
共催:新学術領域研究:「マルチモードオートファジー:多彩な経路と選択性が織り成す自己分解系の理解」
講演者・概要▼
講演者:小松 雅明 (順天堂大学)、池田 史代 (九州大学)、佐藤 美由紀 (群馬大学)、Lazarou Michael (Monash University)、Dagdas Yasin (Gregor Mendel Institute of Molecular Plant Biology)
概 要:現在までに国内外のオートファジー研究は、未曽有の発展をした。しかし、オートファジー研究は、収束に向かう状況にはない。むしろ、新しい発見が更に多くの未知を創出し、解明すべき課題が山積している。実際、従来の概念を超えた謎、特にオートファジーの選択性が明らかになってきた。本シンポジウムでは、オートファジーの選択的分解に焦点を当て、選択性をエンゲージするメカニズムや選択的分解の生理作用を討議したい。
2S04e
日 時:11月4日(木)17:00-19:00 会 場:第4会場 (G402)
生体恒常性および疾患を制御する間質細胞生物学
オーガナイザー:大石 由美子 (日本医科大学)、真鍋 一郎 (千葉大学)
講演者・概要▼
講演者:佐藤 荘 (東京医科歯科大学)、小池 博之 (日本医科大学)、伊藤 美菜子 (九州大学)、北岡 志保 (神戸大学)、住田 智一 (イェール大学)、増田 隆博 (九州大学)
概 要:組織は実質細胞とそれをとりまく間質から構成されます。間質には、血管や線維芽細胞、免疫細胞、組織幹細胞等が存在します。最近の研究から、間質は実質組織を支持するニッチとしてのみならず、実質細胞と相互作用することにより組織恒常性や様々な病態の発症・進展を制御することが明らかになって来ています。近年、シングルセル解析技術の進展はめざましく、間質細胞は、想定以上に時空間特異的な多様性を備えることも分かりつつあります。本シンポジウムでは、間質がリードする生体恒常性と病態の理解を目指した研究を、若手研究者からご紹介いただき、新たな間質細胞生物学について議論を深めます。
2S05e
日 時:11月4日(木)17:00-19:00 会 場:第5会場 (G401)
放射線障害と加齢性傷害:食事の影響
オーガナイザー:大寺 恵子 (東邦大学)、尚 奕 ((国研) 量子科学技術研究開発機構)
講演者・概要▼
講演者:尚 奕 ((国研)量子科学技術研究開発機構)、森岡 孝満 ((国研)量子科学技術研究開発機構)、山内 一己 ((公財)環境科学技術研究所)、大寺 恵子 (東邦大学)、小林 正樹 (東京理科大学)、福井 浩二 (芝浦工業大学)
概 要:生体は、生命活動で発生する活性酸素種などの内因性のストレッサーや電離放射線などの外因性のストレッサーに常に晒されている。いずれのストレッサーもタンパク質、脂質、核酸などの生体高分子に直接あるいは間接的に傷害を与えることが知られている。このような傷害分子の蓄積は、正常な細胞機能を低下させ、癌などの老化関連疾患の発症を高める。生涯に渡るカロリー制限や食事量の制限は寿命を延長し、老化関連疾患の発症を遅延あるいは抑制することが知られている。しかしながら、若齢期で一度受けた短期ストレスや加齢過程で受けた長期ストレスに対する食事(カロリー、栄養素)の影響に関する研究は少ない。本シンポジウムでは、放射線障害や加齢性傷害に対する食事の影響についてユニークな基礎研究を行っている研究者に最近の知見を紹介して頂くとともに、生化学会の会員の皆様とディスカッションをし、更なる研究の発展につなげることを目的とする。
2S06e
日 時:11月4日(木)17:00-19:00 会 場:第6会場 (G302)
生物間相互作用の多様性と統一性
オーガナイザー:松本 靖彦 (明治薬科大学)、宮下 惇嗣 (帝京大学)
講演者・概要▼
講演者:パウデル アトミカ (北海道大学)、宮下 惇嗣 (帝京大学)、石井 雅樹 (武蔵野大学)、宮崎 真也 (長崎大学)、垣内 力 (岡山大学)、倉石 貴透 (金沢大学)
概 要:感染や共生に見られるような生物間の相互作用は、地球上の生命活動のありかたを定める重要な因子である。生物間の相互作用は様々な外的(環境)・内的(生理学的)要因による影響を受け、地球の時空間上でダイナミックに変動している。こうした生物間相互作用の結果、短期的には個体・個体群(単細胞生物の場合は細胞群集)が数を増減させ、長期的には種の生存・淘汰を通して現在の地球における生態系を形成している。生物間相互作用がもたらす生命の姿を紐解くには、生化学的知見に裏打ちされた分子レベルでの理解が必須である。本シンポジウムでは、多様な生物間相互作用に焦点をあてつつも、分子レベルの理解に基づく統一的な見方を探るために、単細胞生物からヒトまでの様々な生物種を対象とした多様なバックグラウンドの研究者を集め、生化学に基づく分子レベルでの生物間相互作用の計測・予測・制御が切り拓く未来について活発な議論を期待する。
2S07e
日 時:11月4日(木)17:00-19:00 会 場:第7会場 (G301)
細胞老化の新潮流
オーガナイザー:河野 恵子 (沖縄科学技術大学院大学)、城村 由和 (東京大学)
講演者・概要▼
講演者:Teh-Wei Wang (東京大学)、山本 拓也 ((国研)医薬基盤・健康・栄養研究所 免疫老化プロジェクト)、高橋 暁子 ((公財)がん研究会がん研究所)、クラスタ カレン (国立シンガポール大学)、河村 佳見 (熊本大学)、河野 恵子 (沖縄科学技術大学院大学)
概 要:細胞老化は1960年代に「試験管内における細胞の不可逆的増殖停止」としてHayflickらにより定義された。がん細胞の研究が盛んであった当時、細胞は最適な増殖条件を与えさえすれば永遠に分裂するものであって、細胞老化は単なるアーティファクトであると考える研究者が大多数であった。しかし約半世紀の時を経た今日、細胞老化が個体老化に寄与することはいくつものエビデンスにより明確に示されており、個体内の老化細胞を一細胞レベルで可視化することすら可能になった。本シンポジウムでは、酵母・ハダカデバネズミ・サル・ヒトなど多様な実験材料を用い、独自の切り口で細胞老化研究を展開している若手・中堅研究者に光を当て、今まさに生まれつつある細胞老化研究の新潮流について議論したい。
2S08e
日 時:11月4日(木)17:00-19:00 会 場:第8会場 (G312)
HUMAN BIOLOGYを志向したミトコンドリア生化学
オーガナイザー:佐邊 壽孝 (北海道大学)、絹川 真太郎 (九州大学)
講演者・概要▼
講演者:絹川 真太郎 (九州大学)、髙田 真吾 (北翔大学)、半田 悠 (北海道大学)、笠原 敦子 (金沢大学)、吉田 陽子 (順天堂大学)、横田 卓 (北海道大学病院)
概 要:ミトコンドリアは健康、老化、並びに、疾患の中核である。私達は、神経由来栄養因子(BDNF)は骨格筋からも産生され、ミトコンドリア生合成と脂質代謝を亢進すること、血中BDNF量は老化や心不全で低下し機能障害誘引となること、などを明らかにしてきた。ミトコンドリアは過剰な運動や心不全、癌、老化などにおいて機能障害を来すと共に、脂肪酸からケトン体へのエネルギー源変換を含めた代謝リモデリングを起こす。その際、体温や酸素濃度、マイオカイン、コハク酸など様々な因子が関与するが、その生化学的実態解明は途についたばかりである。ミトコンドリア生化学に関し、健康、運動、加齢、疾患、を含めた全身状態との関連を統合的に理解するHUMAN BIOLOGYが求められている。ガチガチの分子詳細も欠かせない。本シンポジウムは、若手・中堅研究者が発表を行い、今後の研究方向性や問題点を議論し発展を促す。
2S09e
日 時:11月4日(木)17:00-19:00 会 場:第9会場 (G313)
根圏の生化学
オーガナイザー:白須 賢 (理化学研究所)、吉田 聡子 (奈良先端科学技術大学院大学)
講演者・概要▼
講演者:杉山 暁史 (京都大学)、晝間 敬 (東京大学)、亀岡 啓 (東北大学)、吉田 聡子 (奈良先端科学技術大学院大学)、白須 賢 (理化学研究所)
概 要:根圏は植物の根と多様な生物が共存するユニークなインターフェースであり、生物間そして真核生物である宿主との間で相互作用する場となっている。宿主である植物と生物は一対一で見れば、寄生、片利共生あるいは共生の関係があるといえるが、根圏は、無数といえる相互作用があって非常に複雑であり、環境の変化および根の生長や発達にともないダイナミックに変動している。しかしながら、どのようにして根圏生物の共同体が成立し維持されているか、またメンバーである生物同士、さらには宿主が情報交換をしているはほとんど明らかになっていない。植物そして根圏に生息する生物は、最近のゲノム解析からも、多様な代謝物を生産できる酵素群をコードしていることが明らかになってきているが、その代謝物の機能はほとんど同定されていない。本シンポジウムでは根圏のエキスパートを招聘し、生化学的アプローチによる根圏の理解をめざす。
2S10e
日 時:11月4日(木)17:00-19:00 会 場:第10会場 (G314)
中枢神経系の恒常性維持解明を目指す多角的研究
オーガナイザー:村松 里衣子 (国立精神・神経医療研究センター)、津田 誠 (九州大学)
講演者・概要▼
講演者:村松 里衣子 (国立精神・神経医療研究センター)、津田 誠 (九州大学)、有村 奈利子 (国立精神・神経医療研究センター)、小林 亜希子 (京都大学)、岸 雄介 (東京大学)
概 要:脳と脊髄からなる中枢神経系は、適切な発生機構により制御され、また病態では修復されることで、その恒常性が維持されている。従来より、発生や修復に特化した詳細な研究が盛んに進められているが、最近では、発生と修復の相違点から神経系を制御するような横断的な視点での試みもなされている。特に、グリア細胞や免疫系細胞など、神経細胞以外との細胞間相互作用に着目した研究に注目が集まっており、このようにして発生と修復の相違点を解明することは、神経系の恒常性制御機構を包括的に理解するだけでなく、種々の中枢神経疾患に対する治療シーズの獲得という観点からも重要と期待されている。本シンポジウムでは神経系の発生、修復における最先端の知見を、次世代を担う若手研究者を中心に発表していただき、神経系の発生の理解や疾患克服へ向けた展開の可能性について議論したい。
2S11e
日 時:11月4日(木)17:00-19:00 会 場:第11会場 (G315)
これからの研究者はどうあるべきか?
オーガナイザー:田中 智之 (京都薬科大学)、榎木 英介 (科学・政策と社会研究室)
講演者・概要▼
講演者:豊田 長康 (鈴鹿医療科学大学)、斉藤 卓也 (文部科学省)、田中 智之 (京都薬科大学)、瀧澤 美奈子 (日本科学技術ジャーナリスト会議)
概 要:プロジェクト型研究や任期制の拡大といった近年の科学研究政策の変化は、研究者のキャリアを不透明でリスクの高いものにしており、結果として研究力の低下を招いています。私たちはどうすればこの状況を変えることができるでしょうか?例えば、政策決定者がどう考えているかを理解することや、科学研究を取り巻く人たちとの対話と協働に加わる必要があるかもしれません。また、社会に溶け込む研究者が増えれば、科学研究の支援者は増えるかもしれません。このシンポジウムでは科学研究政策、研究公正、科学コミュニケーション、新たに結成された日本版AAASを取り上げ、こうした問題を考えていただく契機にしていただくことを目的としています。講演後はパネルディスカッションを通じて議論を行う予定です。
2S12e
日 時:11月4日(木)17:00-19:00 会 場:第12会場 (G316)
RNAとRNPの特異的修飾による発現制御機構と生理機能
オーガナイザー:稲田 利文 (東北大学)、齊藤 博英 (京都大学)
講演者・概要▼
講演者:鈴木 勉 (東京大学)、五十嵐 和彦 (東北大学)、齋藤 博英 (京都大学)、魏 范研 (東北大学)、稲田 利文 (東北大学)
概 要:遺伝子発現は生命現象の基盤であり、発現制御の破綻は様々な疾患の原因となる。RNAは、ゲノム情報をタンパク質へ仲介する分子であり、様々な修飾を受けることで機能を獲得する。最近の解析手法の進展によりRNA修飾の重要な生理機能がより明確になり、転写後の発現制御を介した細胞内シグナル伝達や代謝との関連が明らかになりつつある。また、RNAがタンパク質と形成する「RNA-タンパク質複合体(RNP)」は細胞内分子機構の中核をなす。翻訳装置であるリボソームは代表的なRNPであり、特異的な修飾を受けることで、異常翻訳の認識やリボソーム自身の品質管理、さらにはmRNA安定性やタンパク質の局在にも重要な機能を果たす。さらに、RNAやRNP複合体の機能や形成を制御し、細胞を自在に操作するための基本原理も明らかになりつつある。本シンポジウムでは、RNAとRNPの新規修飾とその生理機能解明を目指した最新の研究成果を紹介する。
3S01m
日 時:11月5日(金)9:00-11:00 会 場:第1会場 (G303+304)
共役脂肪酸の新機能解明と認知症予防薬としての可能性
オーガナイザー:羽田 沙緒里 (産業技術総合研究所)、可野 邦行 (東京大学)
講演者・概要▼
講演者:可野 邦行 (東京大学)、羽田 沙緒里 (産業技術総合研究所)、佐野 良威 (東京理科大学)、駒野 宏人 (岩手医科大学)、岸野 重信 (京都大学)
概 要:多様な脂肪酸の中で、機能性成分として共役脂肪酸には様々な効能があることが多くの研究から明らかになってきている。特に共役リノール酸に関して、ガン、動脈硬化、糖尿病等に対して効果があるという報告もあり、サプリメントとしても販売されており安全性が確認されている。共役リノール酸には末梢組織に対する生理活性のみならず、中枢神経系に対しても生理活性を有することが徐々に明らかにされてきており、注目されている。社会の高齢化に伴い、患者数の急増が問題となっている認知症には現在のところ有効な治療薬・治療法が確立されていない。最新の研究成果により、共役型リノール酸のアルツハイマー病様症状を改善する機能を示唆するデータが蓄積しつつある。本シンポジウムではこれまでの共役脂肪酸の知見を共有し発展させるとともに、認知症予防薬としての共役脂肪酸の可能性を提示したい。
3S02m
日 時:11月5日(金)9:00-11:00 会 場:第2会場 (G404)
糖鎖・レクチンを活用した新たな創薬戦略
オーガナイザー:舘野 浩章 (産業技術総合研究所)、鈴木 匡 (理化学研究所)
講演者・概要▼
講演者:原田 陽一郎 (大阪国際がんセンター研究所)、木塚 康彦 (岐阜大学)、下村 治 (筑波大学)、オイナム ラルハバ ((国研)産業技術総合研究所)
概 要:糖鎖は細胞の最も外側に露出し、細胞型のみならず癌化や分化等の細胞状態の変化を鋭敏に反映する。もちろん糖鎖は老化によっても変化する。そのため糖鎖は病態細胞や老化細胞を狙い打ちするための極めて有望な標的となる。組織特異的に発現する内在性レクチンを標的とした医薬品(GalNAc-siRNA)やレクチンを用いたがん等の診断技術(AFP-L3, M2BPGi)は既に実用化されている。また、レクチンは病態細胞に露出した糖鎖を標的化するための薬剤キャリアへの展開も期待される。本シンポジウムでは糖鎖・レクチンを活用した新たな創薬戦略の構築に向けて、基礎から応用まで広く講演頂く。がん関連糖転移酵素の生化学的解析、老化により変化する皮膚幹細胞の糖鎖の機能と応用、がん細胞の挙動を支配する糖代謝、そして膵がんを狙いうちするレクチン医薬品開発について、今後の糖鎖研究を担う勢いのある4名の若手研究者から講演頂く。規定路線の研究では面白くない。糖鎖・レクチンを活用した挑戦的な創薬戦略について議論したい。
3S03m
日 時:11月5日(金)9:00-11:00 会 場:第3会場 (G403)
生体分子の高速分子動画撮影の最前線
オーガナイザー:中津 亨 (京都大学)、當舎 武彦 (理化学研究所)
共催:新学術領域「高速分子動画法によるタンパク質非平衡状態構造解析と分子制御制御への応用」
講演者・概要▼
講演者:中津 亨 (京都大学)、當舎 武彦 (理化学研究所)、古谷 祐詞 (名古屋工業大学)、村川 武志 (大阪医科大学)、梅名 泰史 (自治医科大学)、島 扶美 (神戸大学)
概 要:日本のX線自由電子レーザー施設であるSACLAにおいて、X線レーザーが発振され今年で10年となる。その間、構造生物学の分野では、目覚ましい進展があった。放射光施設においては全自動でX線回折強度データが収集できるようになり、さらには電子顕微鏡の発展により膜タンパク質やタンパク質複合体の立体構造決定がより可能となってきた。しかし、静的な情報だけでは生体分子をきちんと理解できず、動的な情報が必要であるという理解がより深まりつつある。それと相まって、SACLAを用いた研究手法の開発が進み、時々刻々と変化するタンパク質や酵素の動的な構造を観測できるようになってきた。本シンポジウムではX線自由電子レーザーを用いた研究を中心に、分光法や光解離性化合物など様々な手法と融合した「高速分子動画撮影」に関する最新の研究を講演していただき、タンパク質や酵素が持つ本来の機能を議論する。
3S04m
日 時:11月5日(金)9:00-11:00 会 場:第4会場 (G402)
老化と生体防御システム
オーガナイザー:高橋 良哉 (東邦大学)、樋上 賀一 (東京理科大学)
講演者・概要▼
講演者:丸山 光生 (国立長寿医療研究センター)、清水 孝彦 (国立長寿医療研究センタ)、樋上 賀一 (東京理科大学)、高橋 良哉 (東邦大学)
概 要:日本の超高齢化社会が進むに伴い、いろいろな研究分野において「老化」に対する関心が高まっている。本シンポジウムでは、日本基礎老化学会のメンバーとして長年、老化の基礎研究に携わってきた研究者が、老化をどのように捉え、どのように研究を進めているかについて紹介する。シンポジウムテーマは、「老化と生体防御システム」である。分子レベルから個体レベルの生体防御システムの加齢変化について取り上げる。本シンポジウムでは、特に、少しでも老化に関心のある生化学会会員の皆様との意見交換を活発に行うことに重点を置く。「老化」という生命現象について異なる分野の研究者が互いに議論することで新たな老化研究に対する考え方が生まれ、それらがそれぞれの分野における老化研究の発展につながることを期待する。
3S05m
日 時:11月5日(金)9:00-11:00 会 場:第5会場 (G401)
生化学で切り込む循環器研究の最前線
オーガナイザー:坂上 倫久 (愛媛大学)、大坂 瑞子 (東京医科歯科大学)
講演者・概要▼
講演者:大坂 瑞子 (東京医科歯科大学)、宮崎 拓郎 (昭和大学)、山城 義人 (筑波大学)、増田 治史 (東海大学)、岩田 洋 (順天堂大学)、坂上 倫久 (愛媛大学)
概 要:血管機能の異常は、組織恒常性破綻を引き起こし、動脈硬化関連疾患や心疾患などへのドミノ倒しの原因となる。このような負の連鎖の元となる現象を紐解き、ドミノピース一つ一つを正しく理解することは、血管石灰化などの不可逆的な血管病態を未然に防ぐこと、あるいは不可逆を可逆的なものに変換することにもつながる。本シンポジウムでは、分子・細胞・個体・臨床検体など、ミクロからマクロまでの多様な角度から最新の生化学テクノロジーを武器に循環器疾患に挑む研究者が集結し、研究成果を紹介するとともに、基礎-臨床研究者が融合する新しい血管生物学の展開と将来展望について議論を深めたい。
3S06m
日 時:11月5日(金)9:00-11:00 会 場:第6会場 (G302)
Wntシグナル経路による細胞機能制御の新展開
オーガナイザー:山本 英樹 (大阪大学)、菊池 浩二 (熊本大学)
講演者・概要▼
講演者:石谷 太 (大阪大学)、紙崎 孝基 (神戸大学)、築山 忠維 (北海道大学)、菊池 浩二 (熊本大学)、山本 英樹 (大阪大学)
概 要:Wntは細胞内において様々なシグナル経路を活性化することにより、胎生期の器官形成や成体の恒常性維持に重要な機能を果たす。そのため、Wntシグナル経路の異常が発癌等の疾患にも深く関連する。これまでに、Wntシグナル経路構成分子であるβ‐カテニンの分解機構は詳細に明らかにされてきたが、Wntシグナル経路の活性調節や細胞応答を制御する分子機構、他のシグナルとのクロストークの全貌は明らかにされていない。本シンポジウムでは、各領域でWntシグナル研究を進める研究者が一堂に会し、Wntシグナルによる新たな細胞機能制御に関する研究成果を紹介する。本シンポジウムがWnt研究の新しい時代を切り開く端緒となることを期待している。
3S07m
日 時:11月5日(金)9:00-11:00 会 場:第7会場 (G301)
医食同源:食と自然治癒力
オーガナイザー:小林 麻己人 (筑波大学)、内田 浩二 (東京大学)
講演者・概要▼
講演者:米代 武司 (東京大学)、大西 康太 (徳島大学)、板倉 正典 (東京大学)、白木 琢磨 (近畿大学)、伊東 健 (弘前大学)
概 要:医薬による治療だけでは経済的・社会的に対応しきれない時代を迎えており、「食」による健康増進や疾患予防が注目されている。「食」の活用は新しい戦略ではなく、『医食同源』といわれるように日常から体に良い食事をとることにより健康を保ち、病気を予防することが最善の医療という古くから知られた考えである。大事なことは「食」が直接疾患原因を押さえ込むのではなく、我々の体が生まれながらにもつ「自然治癒力」を増強させて効力を発揮する局面が多いことである。これは多くの医薬品にも言えることでもあり、「自然治癒力」はまさに『医食同源』の根本ともいえる。我々がどのような「自然治癒力」をもち、どのように「食」や「薬」により増強されるかを知ることは、疾患予防戦略における重要な鍵となる。本シンポジウムでは、こうした「自然治癒力」の分子基盤解明に挑戦する気鋭の若手研究者らを招き、『医食同源』研究に関する最新の話題提供をしていただく。
3S08m
日 時:11月5日(金)9:00-11:00 会 場:第8会場 (G312)
生命科学におけるデータ駆動型アプローチ
オーガナイザー:井倉 毅 (京都大学)、本田 直樹 (広島大学/京都大学/自然科学研究機構)
講演者・概要▼
講演者:井倉 毅 (京都大学)、杉村 薫 (東京大学)、青木 一洋 (自然科学研究機構)、本田 直樹 (広島大学/京都大学/自然科学研究機構)
概 要:近年、生物学の分野では、生体イメージングや次世代シーケンサーを代表とする計測技術などのハイスループットな研究手法の発展に伴い大量のデータが蓄積されている。今まさに生物学は数理的アプローチとの融合を必要としている。しかしながら、複雑かつ動的な生命現象の背後に潜む規則性やメカニズムをデータから抽出するための融合研究は、ほとんど浸透していないのが現状である。この問題に対して、生化学で主に行われてきた要素還元的アプローチと数理モデリングに基づく構成論的アプローチとの接点を見出すことで、それらの乖離を埋める必要がある。そこで本シンポジウムでは、異なる方向性で研究を行ってきた実験および数理研究者が一堂に会することで、乖離の問題点を抽出し、今後の生化学研究の新たな視点を提供したい。
3S09m
日 時:11月5日(金)9:00-11:00 会 場:第9会場 (G313)
個体と臓器のスケーリング機構
オーガナイザー:仁科 博史 (東京医科歯科大学)、松井 秀彰 (新潟大学)
講演者・概要▼
講演者:仁科 博史 (東京医科歯科大学)、兪 史幹 (理化学研究所)、大森 義裕 (長浜バイオ大学)、山口 智之 (東京大学)、豊島 文子 (京都大学)、二階堂 雅人 (東京工業大学)、松井 秀彰 (新潟大学)
概 要:動物は進化の過程で生息環境に適応しつつ、個体サイズ(体長や体重)を多様化させてきた。生物学者は、機能と関連させて個体サイズの制御機構(スケーリング機構)の解析を行ってきた。しかし、マウスとゾウの個体サイズの違いを説明しうる遺伝要因依存性の個体スケーリング機構や、環境要因依存性の個体スケーリング機構、特定の個体サイズでの臓器の配置・相互作用・サイズなどの臓器スケーリング機構、これらの重要な課題は未解明のままである。このような状況下、ゲノムインフォマティクス・各種オミクス解析などを駆使することにより個体や臓器のスケーリング機構の本格的解明に着手できる環境が整ってきた。本シンポジウムでは、スケーリング機構の最前線の研究を紹介する。
3S10m
日 時:11月5日(金)9:00-11:00 会 場:第10会場 (G314)
リン酸化による脳活動の遷移
オーガナイザー:内匠 透 (神戸大学)、高野(早田) 敦子 (大阪大学)
講演者・概要▼
講演者:内匠 透 (神戸大学)、永井 拓 (藤田医科大学)、北園 智弘 (筑波大学)、戸根 大輔 (理化学研究所)、高野(早田) 敦子 (大阪大学)
概 要:タンパク質のリン酸化が細胞内シグナル伝達として極めて重要なことはこれまでの多数の生化学研究で明白である。神経系においても、リン酸化はシナプス可塑性や記憶・学習などの脳機能に関わることはよく知られた事実である。また、概日リズムだけでなく睡眠のホメオスタシスにもタンパク質のリン酸化が関わることが最近明らかになってきた。さらに、気分の状態にリン酸化が関わることが分かりつつあり、言わばタンパク質のリン酸化は脳の状態を決定する重要なステップと考えることができるような時代になった。タンパク質のリン酸化によって影響を受ける脳状態の変化に関して、最近の話題を提供し、議論したい。
3S11m
日 時:11月5日(金)9:00-11:00 会 場:第11会場 (G315)
酵素だョ!全員集合-今年も酵素を見つめ直す2021-
オーガナイザー:平林 佳 (東京理科大学 )、和田 啓 (宮崎大学)
講演者・概要▼
講演者:和田 啓 (宮崎大学)、藤間 祥子 (奈良先端科学技術大学院大学)、高橋 一敏 (味の素㈱)、中村 顕 (学習院大学)、中村 照也 (熊本大学)、田中 良樹 (㈱アグロデザイン・スタジオ)
概 要:200年近い生化学史は同時に、“酵素"研究の歴史でもある。生化学の歩みでは、新たな現象の発見や技術革新の恩恵を受けて、時代によって様々な流行が生まれてきたが、酵素は常に生化学の中心にあった。古くは制限酵素やポリメラーゼから、現代のCRISPR/Cas9に至るまで、その存在なしに生化学を語ることはできない。そして、今なお酵素は注目の的にある。COVID-19研究の最前線においても、ウイルスの受容体は酵素ACE2であり、侵入過程には種々のプロテアーゼが重要な役割を担っている。いつの時代でも研究者達を魅了してやまない“酵素"を、生化学の祭典で今年も見つめ直す機会を作りたい。本シンポジウムの演者は、古くから酵素を研究する熟練研究者ではなく、これからの酵素研究を担うジェンダーレスな若手研究者で構成する。古典的な酵素研究から、先端的手法を駆使した斬新な視点、産業界での応用開発など、多彩な立場から酵素の未来のカタチを描きたい。
3S01a
日 時:11月5日(金)14:50-16:50 会 場:第1会場 (G303+304)
感染症と脂質代謝、オルガネラ動態
オーガナイザー:山下 純 (帝京大学)、花田 賢太郎 (国立感染症研究所)
講演者・概要▼
講演者:熊谷 圭悟 (国立感染症研究所)、山本 瑞生 (東京大学)、木村 美幸 (富山大学)、新崎 恒平 (東京薬科大学)、板部 洋之 (昭和大学)、桑田 浩 (昭和大学)、谷川 和也 (帝京大学)、林 康広 (帝京大学)
概 要:人類はこれまでに何度となく感染症の驚異に晒され、それを克服してきた。昨年来の新型コロナウイルスの全世界的な蔓延、すなわちパンデミックは多くの死者をだすとともに、社会生活に大きなダメージを与えている。この脅威に立ち向かうため、多くの医療従事者や研究者が日々努力している。本シンポジウムは、生化学に基盤をおく研究者が感染症の克服を考えることの一助としたいと企画したものである。病因微生物は、宿主の細胞機能を巧みに利用して、感染、複製、寄生などを行っている。ある種の細菌は宿主の脂質合成やオルガネラ動態をハイジャックして寄生することが知られている。また、ウイルス感染の初期過程にはオルガネラ膜の融合など動態が関与する。本シンポジウムは微生物の「生存戦略」を理解するため、脂質代謝、オルガネラ動態、感染症をテーマにする研究者の最近の研究を紹介する。
3S02a
日 時:11月5日(金)14:50-16:50 会 場:第2会場 (G404)
糖鎖が制御する間質-細胞ネットワークと生体機能
オーガナイザー:岡島 徹也 (名古屋大学)、萬谷 博 (東京都健康長寿医療センター)
講演者・概要▼
講演者:岡島 徹也 (名古屋大学)、竹内 英之 (名古屋大学)、萬谷 博 (東京都健康長寿医療センター)、佐藤 ちひろ (名古屋大学)、北川 裕之 (神戸薬科大学)、川島 博人 (千葉大学)
概 要:糖鎖は細胞外の間質を構成する主要因子として位置付けられている。間質と細胞間の相互作用における糖鎖の機能的な重要性については、様々な糖タンパク質の解析を通じて広く認識されている。しかしながら、相互作用の総和としてはたらく間質-細胞ネットワークにおける糖鎖の統合的な機能や生体機能との関連性の理解は、未だ進んでいない。本シンポジウムでは、間質-細胞相互作用における代表的な糖鎖機能の紹介を通じて、糖鎖が制御する間質-細胞ネットワークと生体機能における役割について議論する。
3S03a
日 時:11月5日(金)14:50-16:50 会 場:第3会場 (G403)
研究開発領域紹介:「プロテオスタシスの理解と革新的医療の創出」
オーガナイザー:永田 和宏 (JT生命誌研究館)、遠藤 玉夫 ((地独)東京都健康長寿医療センター研究所)
共催:国立研究開発法人日本医療研究開発機構
講演者・概要▼
講演者:永田 和宏 (JT生命誌研究館)、岩井 一宏 (京都大学)、岩崎 信太郎 (理化学研究所)、伊藤 拓宏 (理化学研究所)、有本 博一 (東北大学)、矢木 宏和 (名古屋市立大学)、小林 妙子 (京都大学)、遠藤 玉夫 (東京都健康長寿医療センター研究所)
概 要:AMED-CREST/PRIMEでは、令和2年度に研究開発領域「プロテオスタシスの理解と革新的医療の創出」を発足させた。本領域においては、タンパク質が翻訳され生成してから、最終的に分解を受けるまでの分子基盤の理解に基づいて、神経変性疾患などの種々の難病に対して、革新的な治療戦略につなげることを目標としている。本領域の掲げる「プロテオスタシスの理解」には、翻訳制御や翻訳後修飾、フォールディング過程およびタンパク質分解までを含めた、タンパク質品質管理機構の全般が含まれ、それらを如何に疾患の病態理解につなげ、治療戦略につなげるかが問われている。今回のシンポジウムでは、本領域の研究開発統括から領域の概要を紹介するとともに、領域アドバイザーから関連研究に関する話題提供、さらに第一期の採択者から、これまでの研究内容および本領域における研究計画について紹介する。これらを参考に、次年度の更なる応募や領域外連携を期待したい。
3S04a
日 時:11月5日(金)14:50-16:50 会 場:第4会場 (G402)
ニューノーマル時代に向けたステロイドホルモンと疾患研究の新展開
オーガナイザー:矢澤 隆志 (旭川医科大学)、奈良 篤樹 (長浜バイオ大学)
講演者・概要▼
講演者:矢澤 隆志 (旭川医科大学)、山崎 広貴 (慶應義塾大学)、原口 省吾 (昭和大学医学部)、諏佐 崇生 (帝京大学)、浅田 秀基 (京都大学大学院医学研究科)、永田 さやか (宮崎大学)、奈良 篤樹 (長浜バイオ大学)
概 要:ステロイドホルモンは、生体の恒常性に必要不可欠であり、疾患の発症や治療にも深く関わる。昨今のCOVID-19においても、デキサメタソンがサイトカインストーム抑制に使用されたり、レニンーアンジオテンシン-アルドステロン系を介した高血圧症やアンドロゲンがACE2を介して重症化リスクを上昇させることが報告されている。その一方で、ホルモン投与による副作用や病態との関連を評価する難しさも指摘されており、これらのステロイドの作用や調節機構のさらなる解析は病態の包括的な理解に不可欠である。本シンポジウムでは、このような研究を行う基礎・臨床分野の中堅・若手の気鋭な演者に、最新の研究成果と共に、各自の関連分野における今後の研究の方向性についても講演してもらう。BC・ADをテーマとする今大会において、本シンポジウムが、ニューノーマル時代に向けたステロイドホルモン研究の新展開を議論する機会となることを期待する。
3S05a
日 時:11月5日(金)14:50-16:50 会 場:第5会場 (G401)
フェロトーシスを含む脂質酸化を起点とする多様な細胞死研究の最前線
オーガナイザー:今井 浩孝 (北里大学)、山田 健一 (九州大学)
講演者・概要▼
講演者:山田 健一 (九州大学)、井手 友美 (九州大学)、袖岡 幹子 (理化学研究所)、今井 浩孝 (北里大学)、四元 聡志 (東京薬科大学)
概 要:2012年にはじめて報告された抗がん剤により引き起こされる遊離二価鉄を介した脂質酸化依存的細胞死(フェロトーシス)は、カスパーゼ非依存性の非アポトーシス経路の細胞死として、現在最もホットな細胞死研究領域である。この10年の間にその制御因子の同定や病態での役割などが次々に報告されている。一方、脂質酸化の抑制因子であるGPx4はフェロトーシスの制御因子でもあるが、GPx4欠損のみでは、フェロトーシスとは異なる細胞死が誘導されることや好中球細胞外トラップ誘導機構(ネトーシス)にも酸化リン脂質の生成が関与すること、酸化ストレスにより誘導されるネクローシスの新たな分子機構など、酸化脂質の生成部位の違いによって異なる細胞死メカニズムが誘導されることも明らかになってきた。本シンポジウムではフェロトーシスの新たな分子機構や循環器疾患における役割、脂質酸化が起因となる多様な細胞死研究の最前線で活躍する演者の最新の研究内容を報告する。
3S06a
日 時:11月5日(金)14:50-16:50 会 場:第6会場 (G302)
ストレス応答経路による細胞機能制御の新機軸
オーガナイザー:伊東 健 (弘前大学)、親泊 政一 (徳島大学)
講演者・概要▼
講演者:親泊 政一 (徳島大学)、葛西 秋宅 (弘前大学)、岡崎 慶斗 (東北大学)、粂田 昌宏 (京都大学)、尾崎 拓 (岩手大学)、内海 健 (九州大学)
概 要:生体が持つストレス応答機構はダーウィン進化論の中で、より直接的に環境適応に関与する生体機構として生命生存の鍵であり続けている。また、ヒト疾患においては病態を理解する上で、あるいは疾患治療・予防の標的として有望である。ストレス応答機構は細胞レベルから個体レベルに至るまで様々な階層で緻密に連携しており、各階層においてその構成因子間の相互作用が重要である。また、ストレス分子が細胞分化や細胞周期などの制御にも関与するという機能的多重性も数多く報告されている。本シンポジウムでは、小胞体ストレス、酸化ストレス、ミトコンドリアストレス、核膜孔ストレス、リボソームを起点とするストレス応答機構などにおいて最近新たに明らかになったストレス応答分子あるいは分子機構に注目し、生体の生存戦略について考察すると同時にストレス応答機構を利用した人類の健康増進について議論する。
3S07a
日 時:11月5日(金)14:50-16:50 会 場:第7会場 (G301)
エネルギー毒性の生化学を創出する
オーガナイザー:石堂 正美 (国立環境研究所)
講演者・概要▼
講演者:石堂 正美 (国立環境研究所)、中井 里史 (横浜国立大学)、前田 公憲 (埼玉大学)、池谷 皐 (東京大学)、毛内 拡 (お茶の水大学)
概 要:毒性発現機構の理解には生化学的な解析が必須である。化学物質による環境発がん機構の生化学的解析が進み、その健康リスク評価が成功を収めている。一方、ナノ材料や有害エネルギーなどの物理学的因子のそれは不明な点が多く残されたままである。本シンポジウムでは、特に低エネルギーの毒性発現機構を生化学的に理解するために多角的なアプローチをとる。低エネルギーによる健康リスクの実際を紹介し、低エネルギーによる毒性発現機構について量子生物学的、分子生物学的、神経科学的あるいは物理学的側面からの理解を深め、エネルギー毒性の生化学を築く。
3S08a
日 時:11月5日(金)14:50-16:50 会 場:第8会場 (G312)
モダリティ多様化時代における心血管研究の最前線
オーガナイザー:山城 義人 (筑波大学 )、中嶋 洋行 (国立循環器病研究センター)
講演者・概要▼
講演者:松永 行子 (東京大学)、福井 一 (国立循環器病研究センター研究所)、内藤 尚道 (大阪大学)、福原 茂朋 (日本医科大学)、横山 詩子 (東京医科大学)、洲崎 悦生 (順天堂大学)
概 要:生化学および分子生物学を基軸とした生命科学関連領域の急速な発展に伴い、モダリティ(解析手段)の多様化とそれを有効活用する術の議論が近年高まっている。また、心臓-血管における恒常性の維持には、各種の細胞が独自性と多様性を発揮して機能を適正に制御することが重要であることから、多彩な生命現象を包括的に理解するための多層的な解析アプローチが必須となる。本シンポジウムでは、心血管系の恒常性維持において、独自のモダリティを活用しながら研究を推進する研究者にご講演いただき、1細胞解析、組織幹細胞解析、ライブイメージング、マトリクソーム、マイクロデバイスや3次元組織イメージングの視点に基づいた解析手法の活用について最新の話題を提供する。会場の方々と共に多角的な視点から議論することを目指し、次のcutting-edgeな研究や解析手法が生まれるきっかけとなることを期待したい。
3S09a
日 時:11月5日(金)14:50-16:50 会 場:第9会場 (G313)
栄養素代謝による細胞制御とその破綻
オーガナイザー:日野 信次朗 (熊本大学)、林 良樹 (筑波大学)
講演者・概要▼
講演者:関谷 元博 (筑波大学)、和泉 自泰 (九州大学)、佐野 浩子 (久留米大学)、進藤 麻子 (熊本大学)、林 良樹 (筑波大学)、日野 信次朗 (熊本大学)
概 要:栄養環境は、個体発生や組織恒常性などあらゆる高次生命現象に強く反映される。また、栄養素やその代謝物がシグナル伝達や遺伝子発現調節において固有の役割を持つことが明らかになるにつれ、その生体制御における役割の理解や医療・産業応用への可能性が注目されている。本シンポジウムでは、多様な生物モデル(マウス、アフリカツメガエル、ショウジョウバエ等)、生命現象(細胞の分化・発生、代謝疾患等)、制御階層(シグナル伝達、転写、エピゲノム等)を専門とする研究者による先駆的な研究成果を紹介し、栄養素代謝物の機能を俯瞰する場を提供する。これらの講演を通して、生体制御の精密性と可塑性を支える栄養摂取の役割やポテンシャルについて議論を深めたい。
3S10a
日 時:11月5日(金)14:50-16:50 会 場:第10会場 (G314)
グリア細胞の機能制御と神経炎症病態
オーガナイザー:遠藤 光晴 (神戸大学)、上野 将紀 (新潟大学)
講演者・概要▼
講演者:池上 暁湖 (名古屋大学)、上野 将紀 (新潟大学)、中嶋 秀行 (九州大学)、篠崎 陽一 (山梨大学)、遠藤 光晴 (神戸大学)
概 要:近年、精神疾患や神経変性疾患をはじめとする中枢神経系疾患の病態に神経炎症が深く関わることが明らかとなってきた。そのため、神経炎症の誘導に関わるミクログリアやアストロサイトなどのグリア細胞の機能を制御し、神経炎症を抑制することによる中枢神経系疾患の病態改善が期待されている。グリア細胞による炎症応答は、中枢神経系の恒常性維持に必須の役割を担い、その多様な機能を介して組織修復や感染防御などを司る一方で、その機能破綻によって神経炎症病態の発症に至ることが明らかになりつつある。本シンポジウムでは、炎症時のグリア細胞の多様な機能がどのように制御されているのか、その巧妙な制御のバランスが如何にして破綻するのかについて、分子・細胞レベルでのメカニズム解明に挑戦している気鋭の若手研究者による最新の知見を紹介するとともに、神経炎症病態の発症機構について多角的に議論したい。
3S11a
日 時:11月5日(金)14:50-16:50 会 場:第11会場 (G315)
相分離メガネを通して見た酵素の機能
オーガナイザー:三原 久明 (立命館大学)、中山 亨 (東北大学)
講演者・概要▼
講演者:浦 朋人 (筑波大学)、中山 亨 (東北大学)、三浦 夏子 (大阪府立大学)、美川 務 (理化学研究所)、三原 久明 (立命館大学)
概 要:近年、タンパク質や核酸などの生体分子が集合することにより液―液相分離し、時間的、空間的に特異的な機能を有する集合体を形成することが明らかとなってきた。既知の様々な生物学的現象が相分離による制御を考えることで見直されつつある。細胞内に数多く存在する代謝酵素群が、いかにして混乱せずに連続的な反応を効率よく行っているのか?という謎についても、相分離の観点からアプローチすることにより新たな理解が生まれると期待される。本シンポジウムでは、代謝酵素複合体、チャネリング等に関する研究において最前線で活躍されている研究者に講演を依頼した。相分離の概念を含む新たな観点から酵素を捉えた議論を行い、酵素研究の新たな時代を切り拓くきっかけとしたい。
口頭発表
ポスター